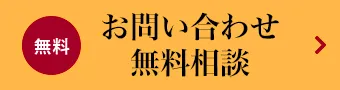一般的に、喪中のタイミングではさまざまな節制が必要となります。
喪が明けるタイミングとなる四十九日は、忌日法要の中でも非常に重要な意味を持つことで有名です。
ただし、具体的に四十九日の意味を正しく理解されている人は少ないのではないでしょうか。
では、四十九日とは一体どのような意味があるのでしょうか。
この記事では、四十九日の意味や亡くなってからの過ごし方を解説します。
四十九日の意味とは?
故人が亡くなられた後に、命日から数えて七日毎に忌日法要が執り行われます。
忌日法要の中でも、特に四十九日法要については重要なものとして認識されています。
故人は、初七日を迎えて以降の7日毎に、生前に犯した罪について閻魔さまによって裁かれるのです。
そして、四十九日のタイミングで来世の行き先が決定されるとされています。
遺族としては、当然極楽浄土へ行けることを強く願うわけですが、そのための法事として四十九日方法が執り行われます。
親族や故人と縁の深かった人が、極楽浄土に無事いけるように、また故人の成仏を祈って法要が執り行われるのです。
古くは、七日毎に忌日法要を実施する形が一般的でしたが、最近では初七日と四十九日のみ法要を執りおこなうケースが多いです。
四十九日は、満中陰とも呼ばれることがありますが、これは古代インドの輪廻転生に基づく考えによるものとなります。
臨終を迎えてから次の生を得る間の期間のことを中陰と呼び、その期間は49日間であるとされています。
中陰の期間は7日毎に中陰供養を執りおこない、49日後は中陰が満ちるか終了するという意味が由来となっているのです。
さらに、四十九日には忌明けのタイミングとなる点にも注目です。
初七日より始まる中陰法要と満中陰の法要を執りおこなうことで、故人は仏様の元へ旅立って遺族は通常の生活に戻ることになります。
四十九日の数え方は、一般的には亡くなった日から数えて49日目となりますが、地域によっては亡くなる前日を1日目と数えるケースもあるので要注意です。
亡くなって四十九日までの過ごし方は?
故人が亡くなられた後、四十九日法要を執りおこなうまでの間は日常とは異なる過ごし方をしなければなりません。
通常は、四十九日までの間は故人の魂が彷徨っていると考えられているため、毎日供養することが望ましいです。
毎日、水と線香をお供えすることになりますが、故人と最も近しい関係であった遺族がおこなうのが一般的です。
また、忌日法要として以下の供養をおこなうことになりますが、先に解説したとおり現代では初七日と四十九日法要のみ執りおこなう形が一般的となっています。
- 初七日(7日目):遺族や親族、友人、知人が参列しての法要や会食をおこなうが、葬儀当日にとりおこなう場合も多い
- 二七日(14日目):遺族のみで供養する場合が多い
- 三七日(21日目):遺族のみで供養する場合が多い
- 四七日(28日目):遺族のみで供養する場合が多い
- 五七日(35日目):遺族のみで供養する場合が多い
- 六七日(42日目):遺族のみで供養する場合が多い
- 七七日(四十九日)
してはいけないこと
四十九日までの間は忌中となるわけですが、忌中には基本的にしてはならないことが多く存在します。
特に、以下のような行事や行動は避けるべきとされています。
- 七五三
- 正月祝い
- 結婚式
- 大きな買い物
- 神社への参拝
- 飲み会への参加
- 神棚を開ける行為
それぞれ、してはならない理由について詳しく解説します。
七五三
七五三とは、子どもが3歳、5歳、7歳になったタイミングで執りおこなう儀式です。
七五三の由来としては諸説あるものの、最も有力なものとして平安時代から宮中で執りおこなわれていた、3つの儀式が由来であるとされています。
現代に比べ、医療の発達が未熟で衛生面も芳しくなかった時代では、子どもの死亡率が非常に高かったのです。
そこで、7歳までは神のうちとして扱われて、7歳になって初めて一人前であると認められていました。
それだけ、子どもが無事に育つことは大きな喜びであったため、七五三として神様に感謝してお祝いしていた歴史があります。
以上より、七五三はお祝いのイベントとなるため、忌中に執りおこなうのはふさわしくないのです。
正月祝い
正月祝いとして、門松や鏡餅、しめ縄などは避けて、家の外には正月飾りをしないようにします。
また、初詣に出かける場合がありますが、後述しますが神社への初詣は控えるべきです。
お年玉についても、お祝いの意味があるため「お小遣い」などの形で渡すのが一般的です。
ほかにも、年賀状を出す行為も控えるべき行動として知られています。
結婚式
結婚式は、人生においても大きなイベントの一つとなりますが、お祝いごととなるため忌中に結婚式を挙げるのは基本避けるべきです。
また、結婚式に招待されている場合も忌中となった場合は欠席の連絡を入れて、 「後日お祝いさせてください」などと伝えるのがよいです。
大きな買い物
家や自動車など、金額の大きなものを購入する買い物は、親戚や周囲の方の目もあるため避けるべきとされています。
ただし、自動車については地域によっては生活必需品であり、予め買い替え予定で納車待ちであった場合は、過度に気にすることはありません。
神社への参拝
忌中は、神社への参拝をおこなってはなりません。
なぜ神社への参拝を避けるべきかと言えば、神道においては人や動物の死を穢れとしているためです。
よって、神社へ足を踏み入れること自体を禁じています。
なお、忌中であったとしても寺院へのお参りであれば問題なくおこなえます。
飲み会への参加
飲み会など、盛り上がるような場所への参加は、忌中は避けるべきとされています。
また、旅行なども忌中は避けて、忌明けのタイミングでおこなうようにしましょう。
神棚を開ける行為
忌中においては、神棚封じをおこなうのが一般的です。
神棚封じとは、家族が亡くなられた際に家の神棚を閉じ、神様に目隠しをするような形で白い半紙を神棚の前へ貼り付けて封じる行為のことです。
神棚封じは故人と同居していた家族以外の方がおこない、忌中は神棚を封じたままにしなければなりません。
なぜ神棚封じを執りおこなうのかと言えば、神様が死の穢れに触れないためとされています。
神道では、古来より神様が穢れに触れると神力が失われると信じられてきました。
人が亡くなられた際に神棚を封じる目的としては「穢れにより死の気配が濃くなる期間、家の神様を守るためです。
よって、神棚を開ける行為自体も忌中にはタブーとなります。
四十九日までにすること
四十九日を迎えるまでの間に、遺族としては準備が必要になるものがあります。
特に、以下を漏れなく準備しなければなりません。
- 仏壇の用意
- お墓の準備
- 本位牌の準備
準備が必要な各項目について、詳しく解説します。
仏壇の用意
四十九日以降は、それまで使用していた後飾り壇から仏壇へと供養の方法が切り替わります。
よって、もし仏壇を持っていない場合は新たに用意しなければなりません。
このタイミングで、お参りの道具だけでなく手を合わせる対象となるご本尊や脇仏も併せて準備しなければなりません。
以上のような仏具は礼拝仏具と呼ばれており、位牌と同様に魂入れする必要があります。
よって、一般的には四十九日法要の際に一緒にお経上げする形が一般的です。
仏壇を継承する場合
仏壇については、特に譲渡について定めたルールはなく、継承や譲渡することに特に問題はありません。
宗派によっては宗派用仏壇もあり、譲り受けた仏壇が全宗派で使用できるかどうかを確認する必要があります。
もし仏壇を引っ越しさせる場合は、引越し前に魂抜きをおこない、引越し後に魂入れしなければなりません。
お墓の準備
一般的な認識として、四十九日までにお墓を建てた上で納骨したいという場合が多いです。
ただし、必ずしも四十九日までにお墓を経てて納骨しなければならない決まりはありません。
もし、四十九日に納骨したい場合は、以下の流れで進める必要があります。
- 納骨先を検討する
- 納骨先の石材店に彫刻を依頼する
- お寺に納骨の法要を依頼する
- 石材店に納骨式の準備を依頼する
- 納骨に必要な書類を準備する
- 納骨式参列者へ連絡する
- 供物、会食、引き出物を準備する
納骨する際には、埋葬許可証が必要となります。
許可証については、死亡届と交換する形で住居している市区町村の役場で受領可能です。
許可証がないと納骨を進められないので、必ず入手してください。
本位牌の準備
本位牌について改めて解説すると、四十九日の忌明けを迎えた後に仏壇に安置される位牌のことを指します。
白木位牌から本位牌に替える目的としては、亡くなられた方が四十九日までは行き先が定まらず彷徨っているため、忌明けを過ぎて初めて成仏すると考えられているためです。
成仏する際には、その証として本位牌に替えることになります。
本位牌には、大きく以下3つの種類が存在します。
- 塗位牌:最も普及している本位牌であり、漆を塗り重ねて金箔などで装飾されている
- 唐木位牌:黒檀や紫檀などの耐久性に優れた天然木を使用して、木目を生かしている特徴がある。
- 回出位牌:台座の上に札板を収納する箱があるタイプの位牌。戒名を記す札板が数枚収納できる
本位牌には、位牌に刻字する項目として以下がありますが、宗派や地域によって異なります。
- 戒名
- 梵字
- 命日
- 俗名
- 享年
なお、通常は注文から完成までに約2週間必要となるため、早めの準備が必要です。
まとめ
四十九日を迎えるまでの間、忌中となるため日常生活を送る上で注意すべき点が多々あります。
また、四十九日法要に向けて準備しなければならないことも多く存在します。
今回紹介したポイントを基に、四十九日を迎えるまでの間の過ごし方に注意しましょう。
日本終活セレモニーでは、葬儀などに関する情報を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。