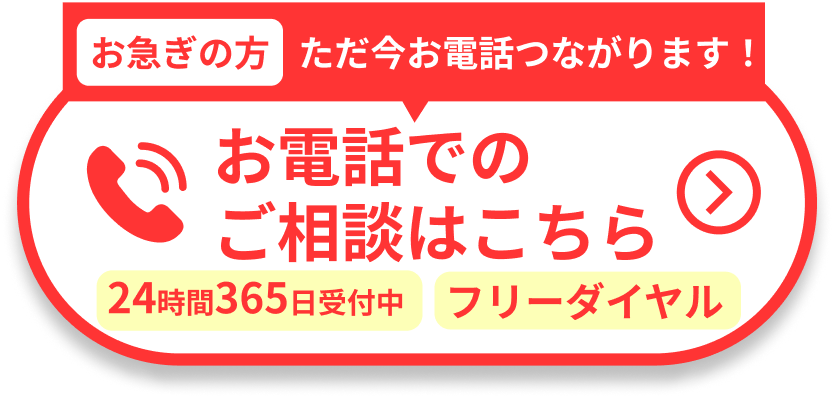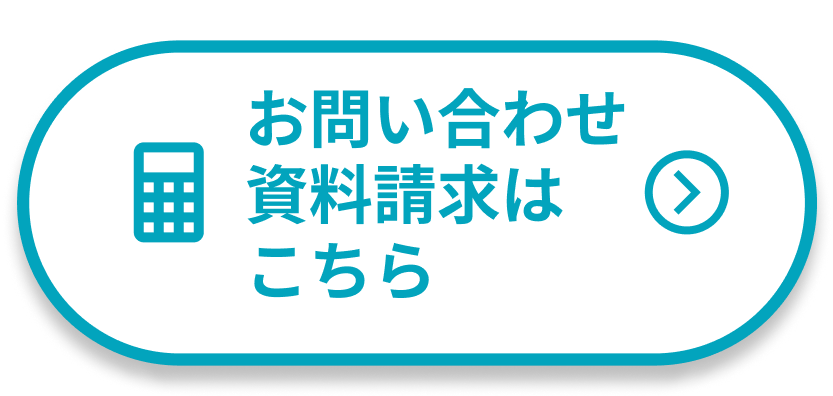参列者のマナー
まずは、参列者側の知っておくべきマナーや注意点について解説いたします。服装は喪服じゃくても良いのです
お葬式の時の服装は黒の喪服と思っていませんか?葬儀時の服装のマナーはお通夜とお葬式の時では異なります。 そもそも、喪服でなけらばならないというマナーはありません。大切なことは「故人の死を悼む」という気持ちが表れることです。本来喪服とは、遺族や近親者が喪に服するための衣装です。飾りのない色も地味な平服でも構わないのです。 男性は地味な色のスーツと黒のネクタイ、黒の靴がよいでしょう。女性の場合も 地味なスーツかワンピースに黒の靴を選びましょう。また、アクセサリーは、パールのネックレスやブローチであればは用いてもよいでしょう。 余談ですが、日本の喪服が黒になったのは、明治維新後の大久保利通卿の葬儀の時に欧米の喪服の色に合わせたのが始まりだそうです。お通夜の時の服装
お通夜の時に、あたかも準備をしてあったかのように喪服を着てくることを嫌がる声もあります。お通夜の席では、上述したような平服が無難でしょう。ただし、最近ではお通夜しか参席しないという方も増えています。その場合には、喪の気持ちを表すために喪服で参列することもよいでしょう。葬儀の時の服装
葬儀の服装は、三回忌まででしたら、黒の略礼服がよいでしょう。お持ちでない場合には、上述したような平服でもかまいません。お焼香の作法
焼香とは、仏教おいて香を焚くことを指します。細かく砕いた香(抹香)を指で摘み、パラパラと落として焚く行為ですね。この作法については、仏教宗派によって異なっていますので、ご紹介しましょう。宗派別のお焼香の作法
- 浄土真宗:右手の親指、人差し指、中指の三本で抹香を軽くつまみ、香炉にくべまる。(大谷派は2回)
- 台宗・真言宗・日蓮宗:右手の親指、人差し指、中指の三本で抹香を軽くつまみ、額に押しいただき、香炉にくべまる。
- 臨済宗:右手の親指、人差し指、中指の三本で抹香を軽くつまみ、香炉にくべまる。
- 曹洞宗:右手の親指、人差し指、中指の三本で抹香を軽くつまみ、1回目は額に押しいただき、2回目は押しいただかずに香炉にくべる。
- 浄土宗:右手の親指と人差し指で抹香を軽くつまみ、額に押しいただき、香炉にくべる。
弔辞のマナー
先程服装について触れましたが、弔辞を行なう場合には、改まったお役目ですので、平服ではなく略礼服を着用するべきでしょう。 弔辞は手に持ち、指名されたら席を立ちます。祭壇の前で遺族に一礼したあと、遺影に向かって目を合わせ、深く一礼します。 弔辞を読む際には、声を低くし姿勢を正し、故人に向かって話しかけるように読みます。そして読み終えたら、祭壇に供えて一礼し、席に戻ります。参列できない場合のマナー
葬儀は故人と最後のおわかれをする儀式ですので、無理を押してでも参列したいものです。しかしどうしても参列できない場合には、まず弔電を打ち、弔意を示しましょう。そして当日代理人に名刺をもたせて参列させるか、後日お香典を手紙を添えて郵便書留で送るようにしましょう。 また、弔問に訪れる場合には、事前に連絡を取り日時を決めて、四十九日までには伺うようにしましょう。お悔やみの言葉に気をつけましょう
なんと言葉をかければいいか、思い浮かばない時には、以下のような文章を参考に言葉を用意しておきましょう。- お父様が亡くなられたと聞き、駆けつけてまいりました。こんな悲しいことはありません。お気持ちお察しいたします。
- この度は、誠にご愁傷さまでございます。心からお悔やみ申し上げます。
- (受付で)本当に残念なことで、心からお悔やみ申し上げます。お参りさせていただきます。