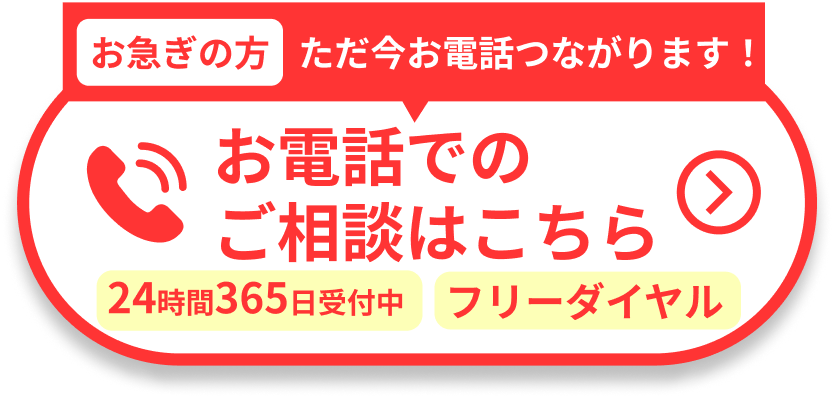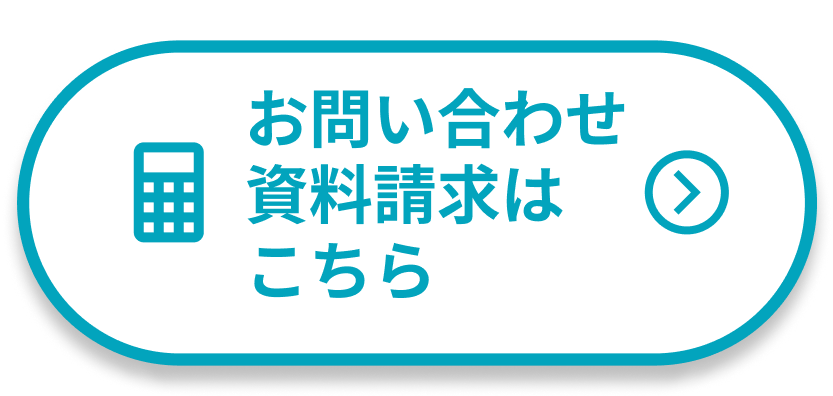目次
家族葬とは
まずはじめに、家族葬について解説します。 家族葬とは、家族や親族、友人、知人を中心として、小規模な葬儀の形式のことを指します。 従来の葬儀と言えば、より幅広い方の参列をもって行うのが一般的でしたが、より近しい関係の方と充実した時間を過ごすという目的もあって、家族葬が主流になりつつあるのです。 家族葬には明確な定義はありませんが、一般的には参列人数は多くても30名程度までで、一般的な葬儀と同じく僧侶をお招きして行うことが多いです。 家族葬が広まった背景には新型コロナウイルスの流行が関係していると説明しましたが、他にも地域のコミュニティーの変化も密接に関係しています。 過去は地元で就職する人の割合が高い傾向があって、産業を盛り上げていこうとする地域の縁はとても強いものがありました。 一方で、現代社会においては進学や就職となれば、すぐに都心部へ移り住むことが当たり前な状況です。 これにより、地域コミュニティーが希薄になりつつあり、もし葬儀を行うとなった場合でも大勢の人を招いて行う意味がなくなっています。 地域コミュニティーの希薄化以外にも、少子高齢化も家族葬が増加した一因となっています。 少子化で兄弟の少ない家庭が増加することで、単純に葬儀における1人あたりの費用的な負担が増加する形となるのです。密葬との違いは?
家族葬と似た葬儀のスタイルとして、密葬があります。 家族葬も密葬も、親族や特に親しかった方のみで行う葬儀のことを指します。 家族葬の場合は、家族葬をおこなうことで葬儀が完結しますが、密葬の場合はその後に再度一般の参列者を呼び葬儀を行うのが一般的です。 よって、本来の意味での密葬とは、一般の参列者が葬儀をする本葬を行う前の段階で、近親者だけで行う葬儀のことを指すのです。 例えば、故人が会社の社長であったり有名人であったりする場合、普通に葬儀を行うと多くの参列者が訪問し、遺族はその対応に追われることになります。 上記事態を避けるために、先に近親者のみで密葬という形でおこなって、故人とのお別れを済ませた後に、一般の参列者を招き本葬を行う流れとなるのです。 多くの参列者が予想される本葬においては、以下のような名前で執り行われるのが一般的です。- しのぶ会
- お別れの会
- 追悼会
家族葬にかかる費用相場と内訳
実際に家族葬を執り行うとなった場合、一般的な葬儀よりも小規模となるために費用的には安くなる傾向があります。 家族葬にかかる費用としては、主に以下のような内訳となります。- 葬儀社に支払う斎場代
- 参列者の飲食代
- 返礼品代
- 火葬料
- 寺院などへのお布施代
葬儀社に支払う斎場代
家族葬の場合でも、一般的には葬儀社に依頼して執り行うのが一般的です。 規模が小さいと言えども、葬儀場などを借りて行う必要があり、また各種手配なども葬儀社の指示のもとで行うと、効率よく行えます。 主に準備すべき項目は、以下の通りです。- 寝台車
- 霊柩車
- 手続き代行費
- 人件費
- 棺代
- 骨壷代
- 位牌
- 遺影
- 祭壇
- 葬具一式
参列者の飲食代
参列者に対して、通夜振る舞いや精進落としなどの飲食接待をおこなうのが通例であり、その費用がかかります。 飲食代は弔問客の数や料理の内容によって大きく左右されますが、主に1名あたり以下のような金額がスタンダードです。- 通夜振る舞い:2,000〜3,000円
- 精進落とし:5,000円程度
返礼品代
一般葬では、参列いただいたことへの御礼として、通夜や告別式の参列者全員に対して会葬御礼を配るのが通例です。 ただ、家族葬の場合はある程度近しい間柄ということもあって、用意しないケースが多く見られます。 また、香典を辞退する場合は香典返しも必要なく、また即日返しでない場合は喪主側が用意することになります。火葬料
火葬場の料金については全国一律ではなく、地域によって相場が微妙に異なります。 また、公営なのか民間であるのかによっても異なる傾向があり。一般的に公営の火葬場では無料で提供されるケースも多いです。 但し、地域によっては数千円から数万円というケースもあり、しっかりと費用をリサーチしておく必要があります。 また、公営の場合はあくまでも地域住民に対してサービスを提供しているだけであって、地域住民以外の方が利用する場合は、通常の数倍の料金が請求される場合もあるので要注意です。 都心部では民間の火葬場が大半であり、また火葬を待つ間の待合室使用料や、の飲食代が別途かかる点も考慮してください。寺院などへのお布施代
仏教の場合はお布施、神式の場合はご神饌料、キリスト教の場合は献金など、葬儀社を介さずに直接お支払いするお礼も必要です。 お布施の場合は、戒名によって相場が微妙に異なり、もし菩提寺がある場合は20万円程度が相場となっています。 ほかにも、お車代や精進落としに出られない場合のお膳代をお渡しする場合、喪主が直接手渡すのが一般的です。 また、火葬場のスタッフや霊柩車や火葬場へ向かう際のマイクロバスなどの運転手に対して、心付けを渡すのが風習となっていましたが、現在では渡さないという場合が増えています。家族葬のトータル費用
葬儀費用の相場としては、全国平均で196万円程度となります。 上記費用には、葬儀社に支払う金額だけでなく、宗教者への支払い、香典返し、その他諸経費を含めたものです。 一方で、家族葬の費用の平均相場は、10人から30人程度の小規模な葬儀での平均額110万円程度となり、一般葬の約半分程度の費用で執り行うことが可能です。 具体的に、葬儀社が提示する家族葬の相場は、基本プランの一日葬では30万円から40万円、二日葬でも40万円から50万円ほどであり、花を増やしたり、精進おとしの手配も依頼するなどのオプションを付けても、プラス数十万円程度で対応できます。 葬儀や告別式も行わない、直葬や火葬式は10万円から行えますが、時間が短くて心の整理がつかないまま故人を見送ることになるのが難点です。家族葬の費用を安く抑えるコツ
家族葬は、一般葬と比較して費用的に安く執り行えますが、さらに費用を抑えるためのテクニックがあります。 主な費用を抑えるための方法としては、以下があります。- 必要最低限のオプションにしておく
- 葬儀の生前予約をしておく
- 参列者の人数を把握しておく
- 宗教・宗派にこだわらない
必要最低限のオプションにしておく
家族葬でも、葬儀社が用意した各種オプションを付けることが可能です。 主なオプションとしては、次のようなものがあります。- 名札を入れられる御供花籠
- 棺に捧げる花束
- 棺とその周辺を飾る花祭壇
- 故人の写真の周りを飾る花
- 焼香台の上に設置する焼香花
- 祭壇周りに並べる花
- 器に生け設置する花
- 棺に入れてご遺体のお顔の周りを飾る花
- 遺族の控え室に設置する花
- 式場の看板の周りに飾る看板花