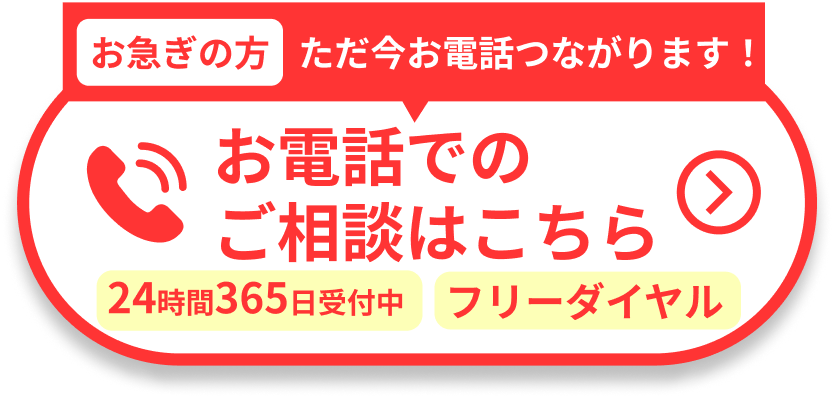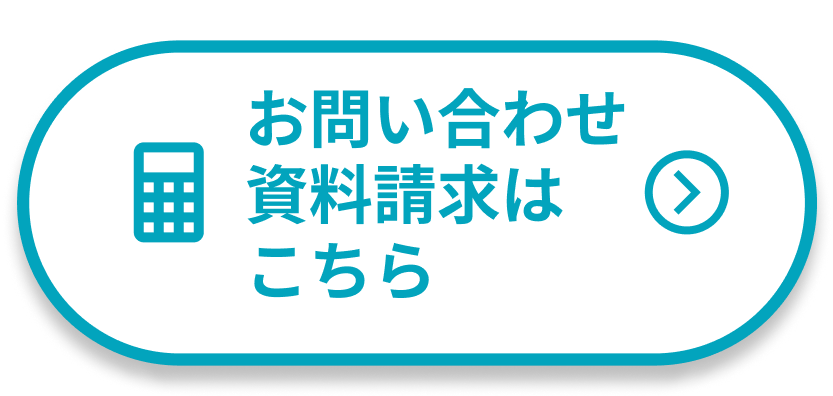目次
四十九日法要の位置づけ
四十九日法要の服装について知る前に、四十九日法要自体の位置づけを正しく理解することが重要です。 四十九日法要とは、故人が亡くなられてから四十九日目に執りおこなう法要のことを指します。 通常、人が亡くなると七日ごとに裁きを受けていると言われています。 そして、亡くなってから四十九日目には最後の裁きを受けて、極楽浄土にたどり着けるかどうかが決まるのです。 遺族として、七日ごとに故人を偲んで故人が極楽浄土に行けるよう冥福を祈る風習があります。 ただし、昨今では二七日法要から六七日法要は省略される傾向にあり、最後の四十九日法要だけをしっかりとおこなうケースが大半です。 四十九日法要は、中陰法要や忌明け法要とも呼ばれる場合が多く、法要当日には自宅や葬祭場などの施設に親族や故人の友達、知人などを招きます。 そして、故人の冥福を祈り供養をおこない、その後は故人を偲びながら会食するのが基本です。 なお、四十九日という考え方は仏教のみとなり、キリスト教では四十九日法要ではなく五十日祭執りおこなう教会が多いです。 50日という数字には、イエス様が復活してから五十日後に、天に上げられたことが由来となっています。 カトリック教会の場合は、三十日目に追悼ミサを執りおこなっています。葬儀や法事における服装には3種類ある
葬儀や法事においては、服装の種類として主に以下3つが存在します。- 正喪服
- 準喪服
- 略喪服
正喪服
正喪服とは、喪服の中でも最も格式の高い服のことを指します。 葬儀では、正喪服を身に付けるのは喪主と三親等までの親族となり、それ以降の親族については準喪服を着用するのが一般的です。 男性の場合、和装では紋付羽織袴を着用し、羽織は黒の羽二重と五つ紋となります。 洋装の場合は、モーニングコートを着用して、ネクタイやベスト、靴下に至るまですべてを黒で統一するのが一般的です。 女性の場合は同じく和装かワンピース、アンサンブル、スーツなどのブラックフォーマルで、和装は染め抜き五つ紋の黒無地の着物です。 洋装は極力肌を隠すようにし、胸元の開いたものは避けて襟の詰まったデザインを選ぶと良いでしょう。夏でも長袖のフォーマルを着用することをおすすめします。 最近では喪主側であっても準喪服を着用する機会が増えており、正喪服を見かける機会はかなり減っています。 和装を希望する場合は持ち合わせがないケースが多いため、葬儀社にレンタルを依頼するのも1つの手です。準喪服
準喪服とは、一般的に想像する喪服のことを指し、一般の参列者として葬儀などに参列する際に用いる服装です。 ただし、参列者以外でも喪主側が準喪服を着用する場合もあります。 準喪服では、男性の場合はブラックスーツを着用します。 女性の場合も、ワンピースやアンサンブル、スーツなどのブラックフォーマルを採用するのが一般的です。 その他装飾品となるベルトやシューズ、バッグについても光沢のある素材は避けて、黒以外は身に着けないようにしましょう。 さらに、女性は正喪服と同じように極力肌の露出を控えた服装を選んでください。略喪服
略喪服は、準喪服よりも堅苦しくなく、普段着に近いスタイルの服装です。 平服で参列してほしい旨を伝えられた場合、略喪服で参列するのが一般的です。 平服といっても、あくまでも略喪服のことであって普段着で参列するのは失礼に値します。 略喪服は、主に三回忌以降の法事や急な弔問などで用いられます。 男女共通で、黒や濃紺などのダークカラーで控えめな服装を選ぶ形が一般的です。 具体的にはブラックフォーマル以外で黒や紺、グレーなどの地味なカラーリングのスーツやワンピースを選びます。 以前は、お通夜は略喪服で参列することがマナーとされていた時代もありました。 ただし、昨今ではお通夜でもブラックフォーマルを選択する人が増えており、略喪服で参列する方はほとんどいません。 もし略喪服で参列するケースでも、男性女性問わず髪型に関する注意点などは準喪服と同じです。四十九日法要における服装
法要の服装は、施主や遺族は正式な喪服を身に付けることが多く、参列者よりも軽装にならないように配慮しなければなりません。 具体的には、親族の場合は準喪服を、親族以外の方は略喪服を着用するのが一般的です。 なお、七回忌以降の法要においては、家族やそれ以外の参列者についても略喪服でよいと考えられています。 ただし、三回忌までは、準喪服や略喪服などを着用してください。 ここでは、性別や子供が四十九日法要で身に付けるものを紹介します。男性の場合
男性の場合で準喪服を身に付ける際には、ブラックスーツを着用して白無地のワイシャツに黒のネクタイなどを選ぶのが無難です。 また、小物なども黒で統一することになりますが、男性の場合はバッグはなるべく使用しないで、必要なものがあれば喪服のポケットに入れるのが一般的です。 略喪服を選択する場合は、黒やグレーといった地味な色合いのダークスーツを着用しましょう。女性の場合
女性の場合で準喪服を身に付ける際には、アンサンブルやワンピースを着用してスカートは短すぎずひざ下丈のものを選んでください。 靴下やストッキング、靴などの小物類は黒で統一するのが一般的です。 女性の場合はアクセサリー系を身に付ける場合が多いですが、四十九日法要では結婚指輪以外のアクセサリーはなるべくつけないようにしましょう。 どうしても身に付けたい場合は、派手な小物は避けてください。 また、バッグを使用する場合は、殺生を連想させることから革製は避けて布製のバッグを使用してください。 略喪服の場合は、黒やグレー、紺色といったワンピースやアンサンブル、スーツを身に付けます。子供の場合
小学生から高校生までの子供が四十九日法要に参列したい場合、服装選びとして大人のように礼服を持っていない場合が多いです。 そこで、喪服代わりになる制服を着用するのが一般的です。 また、制服がないケースでは黒か紺の制服に近い形のコーディネイトを取り入れてください。 女の子の場合は、白か黒のブラウスに黒か紺のスカート、または黒か紺のワンピースを着用しましょう。四十九日法要におけるマナー
四十九日法要においては、服装以外でも守るべきマナーがあります。 特に、以下のようなマナーをしっかりと守って滞りなく進めることが重要です。- お布施について
- 挨拶について
- 返礼品について
お布施について
四十九日法要は僧侶を招いて執りおこなうことになりますが、当然お布施が必要です。 お布施は、一般的には葬儀の際にお渡ししたお布施額の10%から20%程度が目安とされています。 具体的な金額で言えば、一般的な葬儀代が30万円から50万円程度とされていることから、その10%から20%程度となる3万円から5万円程度です。 もし、納骨法要も同時に執りおこなう場合は、全体で5万円から10万円程度が相場となっています。 ただし、僧侶へのお礼としてお渡しする関係上、特段決まりはなくお寺や地域によりことなるのです。 場合によっては、お布施以外にも御車代や御膳料を別途用意する必要がある場合もありますが、相場はそれぞれ5,000円から1万円程度が目安となっています。挨拶について
遺族側は、主に施主側が挨拶を行います。主なタイミングは、法要の開式挨拶、法話後の中締めの挨拶、会食前の挨拶、お開きの挨拶の4回ですが、式の内容によっては異なる場合もあります。 各タイミングでの適切な挨拶は、以下のとおりです。| 挨拶のタイミング | 挨拶の内容 |
| 法要の開式挨拶 | 参列いただいたことへの感謝と読経いただく僧侶の紹介をおこなう。 例)本日は、お忙しい中ご参列を頂きありがとうございます。 ただいまより、故〇〇の49日法要を始めさせていただきます。 それでは〇〇様、よろしくお願いいたします。 |
| 法話後の中締めの挨拶 | 僧侶による法話が終わったら、改めて参列してくださったことへのお礼をお伝えし、その後の納骨式や会食を案内する。 例)おかげさまで、四十九日法要を無事に終えることができました。 この後、心ばかりではございますが別室にてお食事を用意しております。 |
| 会食前の挨拶 | 施主から参列者に向けて、挨拶をする方のお名前や故人様との間柄をご紹介します。 例)本日はお忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで〇〇の四十九日法要もつつがなく終えることができました。つきましては、ささやかではございますがお食事の席をご用意いたしましたので、お時間の許す限り、故人を偲びながらお召し上がりいただければと思います。本日は、誠にありがとうございます。 |
| お開きの挨拶 | 参列者への感謝と、故人様への想いをお伝えし、引き出物のご案内をします 例)本日は御多忙中にも関わらず、亡き○○のためにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。○○も大変喜んでいることと思います。おなごり惜しくはありますが、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたのでお開きとさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 |