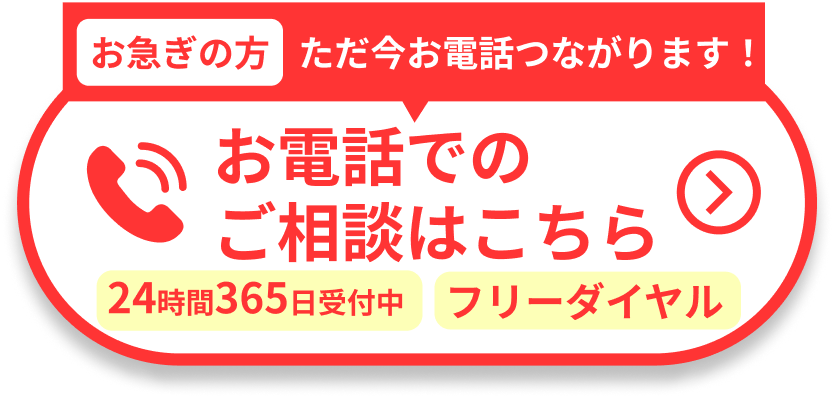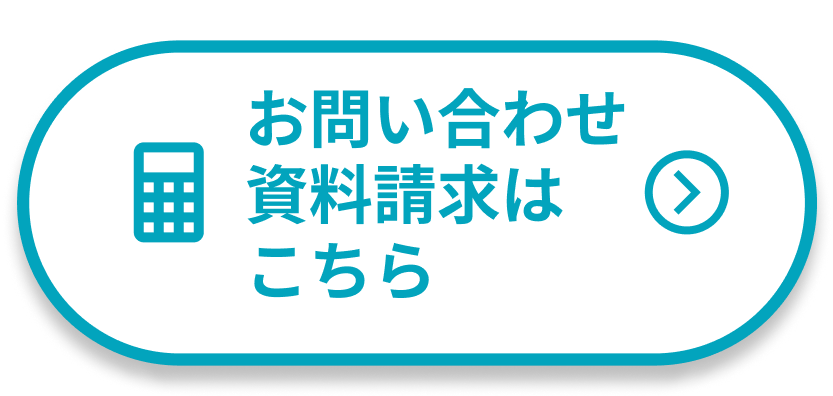目次
葬儀後に必要な行政や相続手続きのリスト
はじめに、葬儀後に必要な行政や相続手続きについて、リストを紹介します。| 期日 | 手続き内容 |
| 死亡から7日以内 |
|
| 死亡から14日以内 |
|
| 死亡から3か月以内 |
|
| 死亡から4か月以内 |
|
| 死亡から10か月以内 |
|
| 死亡から2年以内 |
|
| 死亡から3年以内 |
|
| 死亡から5年以内 |
|
| 分類 | |
| 解約・名義変更 |
|
| 返却手続き |
|
| その他 |
|
死亡から7日以内におこなう手続き
死亡してから7日以内に対応しなければならない手続きは、以下の2つです。- 死亡届の提出
- 埋火葬許可証交付申請書の提出
死亡届の提出
死亡届とは、故人がお亡くなりになったことを行政に報告する届出書のことです。 死亡届は、親族や同居人などが亡くなられた場合に、期日までに役所へ書類を提出しなければなりません。| 申請先 | 死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場 |
| 手続きに必要なもの | 埋火葬許可証交付申請書 |
| 手続き者 | 同居の親族、その他の同居者、亡くなった場所の家屋または土地の所有者、家屋管理人、土地管理人など |
埋火葬許可証交付申請書の提出
埋火葬許可証交付申請書とは、火葬をおこなうために必要となる書類のことです。 埋火葬許可証交付申請書の提出により、埋火葬許可証を得られて火葬をおこなうことができます。| 申請先 | 死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場 |
| 手続きに必要なもの | 死亡届と届出人の印鑑、届出人の身分証 |
| 手続き者 | 基本的に同居の家族がおこなう(代行サービスもあり) |
死亡から14日以内におこなう手続き
死亡から14日以内におこなう手続きとしては、以下があります。- 厚生年金・共済年金・国民年金の受給停止
- 国民健康保険の脱退
- 被扶養者の国民健康保険の加入手続き
- 被扶養者の国民年金の種別変更
- 介護保険資格喪失届
- 住民票の抹消届け
- 世帯主の変更届け
- 児童手当の手続き
- 障害者手帳の返却
厚生年金・共済年金・国民年金の受給停止
故人が加入していた厚生年金・共済年金・国民年金については、亡くなられた後に受給停止の手続きが必要です。 意図的ではなくても、手続きが遅れると不正受給となるため、早急に対応しなければなりません。 なお、正確には厚生年金と共済年金の受給停止手続きは10日以内、国民年金は14日以内に対応する必要があります。| 申請先 | 年金事務所または年金相談センター |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 基本的に同居の家族がおこなう(代行サービスもあり) |
国民健康保険の脱退
健康保険に加入している方が亡くなられた場合、加入をやめるための資格喪失手続きが必要です。 資格喪失に関する手続きについては、もし企業に雇用されている場合は勤務していた会社の担当者がおこなうのが一般的です。| 申請先 | お住まいの市区町村 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 世帯主(代行サービスもあり) |
被扶養者の国民健康保険の加入手続き
もし、健康保険や年金加入者の扶養に入っている場合は、被扶養者資格喪失の手続きと同時に被保険者資格取得の手続きをおこなう必要があります。 国民皆保険の制度があるため、被扶養者資格喪失しても被保険者資格取得が可能なのです。| 申請先 | 住所地の市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 世帯主もしくは同一世帯の人(代行サービスもあり) |
被扶養者の国民年金の種別変更
故人の配偶者が国民年金の第3号被保険者である場合、亡くなられてすぐに仕事に就く予定がない場合、第1号被保険者に該当します。 よって、第3号から第1号への種別変更の手続きが必須です。| 申請先 | 住所地の市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 世帯主もしくは同一世帯の人(代行サービスもあり) |
介護保険資格喪失届
介護保険制度とは、65歳以上で要介護認定を受けており、介護が必要と認定された方、40歳から64歳までの間で特定疾病により介護が必要とされた方に大して、介護サービスを提供するための制度となります。 もし、介護保険に加入している方が亡くなった場合、脱退する手続きをおこなわなければなりません。| 申請先 | 亡くなられた方の住民票がある市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の親族 |
住民票の抹消届け
住民票の抹消届けは、基本的には死亡届を提出すると同時に抹消してもらえる場合があります。 ただし、市区町村によっては別途抹消届を提出しなければならないため、よく確認してください。| 申請先 | 亡くなられた方の住民票がある市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の親族 |
世帯主の変更届け
亡くなられた方が世帯主であった場合、世帯主の変更届を提出する必要があります。 なお、基本的には住民票の抹消届と同じ場所で手続きできるため、同時におこなうのが一般的です。| 申請先 | 亡くなられた方の住民票がある市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの | 届出人の印鑑 本人確認が可能な書類(免許所やパスポートなどの顔写真付きのもの) |
| 手続き者 | 故人の親族 |
児童手当の手続き
児童手当の受給を受けている方がが亡くなられた場合、死亡したタイミングで児童手当の受給資格が消滅します。 配偶者の方などが、亡くなられた方に代わって児童を監護する場合、児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要です。| 申請先 | 市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 対象者を養育する保護者 |
障害者手帳の返却
もし、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている方が亡くなった場合、障害者手帳返還の手続きが必要です。| 申請先 | 市区町村の窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の親族 |
死亡から3か月以内におこなう手続き
死亡から3か月以内におこなう手続きとして、相続放棄と限定承認の申請があります。 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことであり、相続が開始したことを知ってから3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。 また、故人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する限定承認を希望する場合、同時に手続きしなければなりません。| 申請先 | 家庭裁判所 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の親族 |
死亡から4か月以内におこなう手続き
死亡から4か月以内におこなう手続きとして、準確定申告があります。 準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得税についての確定申告となり、以下のようなケースで必要となります。- 被相続人が事業を営んで確定申告していたケース
- 被相続人に副収入を得ており確定申告義務があるケース
- 被相続人の給与額が2,000万円以上となり確定申告義務があるケース
- 被相続人が確定申告によって還付金を受けられるケース
| 申請先 | 税務署 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 相続人 |
死亡から10か月以内におこなう手続き
死亡から10か月以内に必要となる手続きとして、相続税の申告と納付があります。 相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日より、10か月以内に被相続人の住所地の税務署に申告して納税しなければなりません。| 申請先 | 税務署 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 相続人 |
死亡から2年以内におこなう手続き
死亡から2年以内におこなう必要がある手続きには、以下があります。- 各健康保険の埋葬料の申請
- 国民健康保険の葬祭費の申請
- 労災保険の葬祭料と葬祭給付の申請
- 高額療養費の申請(診察月の翌月を1日として2年以内)
各健康保険の埋葬料の申請
各種健康保険に加入している場合、埋葬料の申請が可能です。 故人により生計の全部または一部を維持しており、かつ故人の埋葬を行う方が埋葬のための費用として、一律5万円を受け取ることが可能です。| 申請先 | 健保組合または年金事務所 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の親族 |
国民健康保険の葬祭費の申請
国民健康保険に加入している場合、葬祭費の申請が可能です。 先に紹介した埋葬料と似ている埋葬費ですが、埋葬料を受け取る人がいない場合に給付されるものとなります。 具体的には、故人に親族や生計をともにしていた方がおらず受取人がいない場合、埋葬した方に上限5万円までの実費が支払われることになります。| 申請先 | 健保組合または年金事務所 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の親族 |
労災保険の葬祭料と葬祭給付の申請
もし、故人が労働災害により亡くなり、労災保険に加入している場合は葬祭料と葬祭給付の申請をおこなう必要があります。 葬祭料とは、業務上の災害によって労働者が亡くなった場合、葬儀や法要をおこなった方に対して支給されるものです。| 申請先 | 労働基準監督署 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 基本的に故人の家族 |
高額療養費の申請(診察月の翌月を1日として2年以内)
亡くなられた方が病院でかかった医療費について、自己負担限度額を超えたケースでは、負担額を超えた部分は申請により払い戻しをしてもらえます。 この申請のことを高額療養費支給申請と呼び、対象者が死亡したケースでも相続人が代理人として手続き可能です。| 申請先 |
|
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 基本的に故人の家族(相続人) |
死亡から3年以内におこなう手続き
死亡から3年以内におこなわなければならない手続きとして、生命保険の死亡保険金の請求があります。 生命保険の死亡保険金は、被相続人が加入していた生命保険に対しておこないます。 そして、保険の種類を確認して生命保険会社に連絡して必要な書類を入手してください。| 申請先 | 生命保険会社 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の家族(相続人) |
死亡から5年以内におこなう手続き
死亡から5年以内に手続きしなければならないものとして、以下があります。- 国民年金の寡婦年金請求
- 国民年金の遺族基礎年金請求
- 厚生年金の遺族厚生年金請求
- 労災保険の遺族補償給付請求
国民年金の寡婦年金請求
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が10年以上ある夫が、何の年金も受けることなく亡くなった場合、妻が60歳から65歳になるまでの間支給されるものです。| 申請先 | 国民年金窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 故人の配偶者 |
国民年金の遺族基礎年金請求
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた方が亡くなられた場合、その方によって生計維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(もし障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者、または子が受けることができるものです。| 申請先 | 国民年金窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 給付を受ける者 |
厚生年金の遺族厚生年金請求
遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられた場合、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができるものです。| 申請先 | 国民年金窓口 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 給付を受ける者 |
労災保険の遺族補償給付請求
業務時または通勤中の事故により労働者が死亡した場合に、遺族は労災保険に遺族(補償)給付を請求できます。 なお、労働災害の場合は遺族補償給付、通勤災害の場合は遺族給付と名称が異なります。| 申請先 | 所轄の労働基準監督署長 |
| 手続きに必要なもの |
|
| 手続き者 | 給付を受ける者 |
| 人数 | 遺族(補償)年金 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分(ただし、55歳以上または一定の障害の状態にある妻は175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |