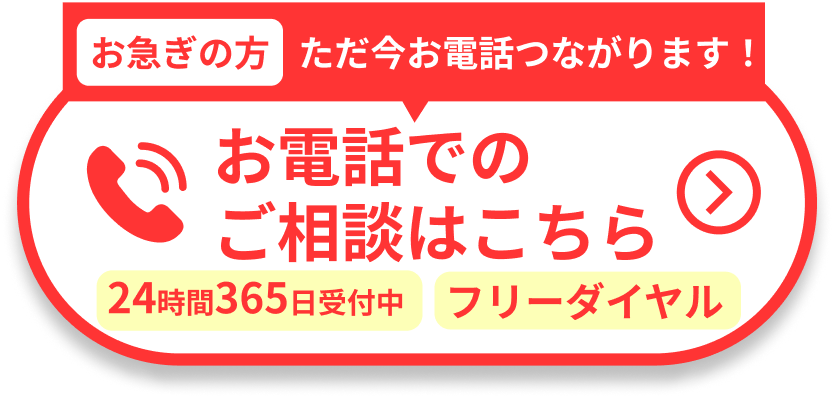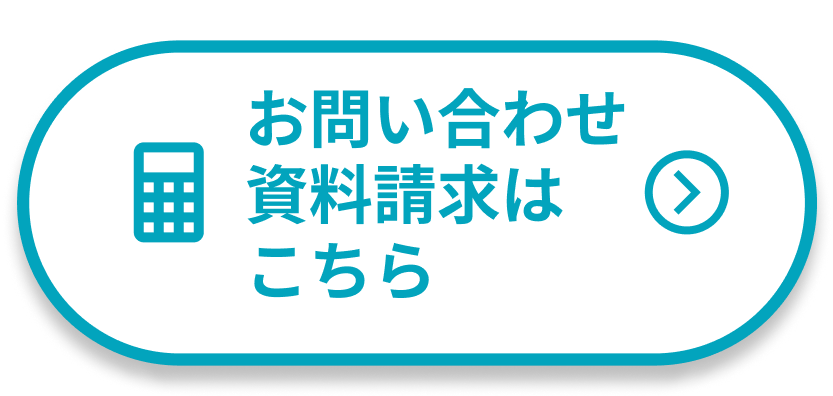目次
葬儀費用の相場と内訳
葬儀を執りおこなう際には、どの程度の費用がかかるのかを把握しておくことが重要です。 これにより、どの程度の費用を負担しなければならないのかを把握でき、資金を準備することができます。葬儀費用の相場
葬儀でかかる費用については、株式会社鎌倉新書が2020年3月に実施した「第4回お葬式に関する全国調査(2020年)」によれば、全国平均で約208万円となっています。 この調査では、ちょうどコロナ禍に入る前のタイミングであったため、実際には葬儀をおこなわなかったり簡略化する形でおこなわれるようになったため、費用的には下がっている傾向があります。 ただし、現在では徐々にコロナ禍以前の状態に戻りつつあるため、約200万円程度の費用がかかると見込んでおくとよいでしょう。葬儀費用の内訳
先に紹介した葬儀費用の相場は、あくまでも葬儀におけるトータルの費用です。 実際には、葬儀においては以下のような費用に分類されます。- 葬式にかかる費用
- 飲食にかかる費用
- 返礼品にかかる費用
- お布施などの費用
| 内訳 | 主な費用 | 費用相場 |
| 葬式にかかる費用 | 火葬場使用料・式場使用料など | 約119万円 |
| 飲食にかかる費用 | 通夜振る舞い・精進落とし・その他飲み物代 | 約31万円 |
| 返礼品にかかる費用 | 会葬者への返礼品や香典返し | 約34万円 |
| お布施などの費用 | 読経料・戒名料・心づけなど | 約24万円 |
葬儀にかかる費用を支払うタイミングは?
葬儀費用については、基本的には葬儀が完了してから支払うのが一般的です。 大まかな流れとしては、まずは利用する葬儀社を決定するために、見積もりを取得することになります。 一社だけでなく、複数の葬儀社に見積もりを取得して、条件のよいプランを提供している葬儀社に依頼するのが一般的です。 そして、正式に契約した上で打ち合わせを実施して、具体的な実施方法を整合して葬儀本番を迎えます。 葬儀が終了した後に1か月以内、短い場合は葬儀終了後即日に費用を支払わなければなりません。 いつまでに支払うかについて、葬儀社との契約内容によって異なるため、しっかりと確認しておく必要があります。支払いは生前に完了させることも可能
葬儀は、基本的に故人が亡くなられた後に依頼することになりますが、場合によっては故人が生前の段階で葬儀社と契約している場合があります。 この場合、残された家族に対して金銭的な負担をかけたくないという理由で、生前のうちに支払いを完了させることも可能です。 また、葬儀社によっては頭金の形で葬儀前に一定の金額を負担しなければならない場合があります。葬儀費用は誰が支払う?
葬儀費用は、平均が200万円を超える場合もあるため、誰が支払うにしても大きな負担がかかってしまいます。 そこで、誰が負担するのかが気になるとことです。 葬儀費用を誰が負担するのかについては、以下のパターンがあります。- 喪主が支払う
- 施主が支払う場合もある
- 親の遺産で支払う
- 相続人で分担して支払う
喪主が支払うのが一般的
喪主とは、葬儀を執りおこなう責任者のことを指し、故人に代わって参列者を迎える遺族の代表者となる存在です。 葬儀の進行部分だけでなく、費用面での負担も基本的に喪主の負担となります。 喪主は、故人が遺言で指名している場合を除いて、基本的に以下の優先順位で決定されます。- 故人の配偶者
- 故人の子供(男性)
- 故人の子供(女性)
- 故人の両親
- 故人の兄弟や姉妹
- 上記以外の親しい人
施主が支払う場合もある
葬儀においては、喪主だけでなく施主を指名する場合があります。 施主とは、葬儀の費用面などの負担をサポートする人のことです。 基本的には、喪主と施主は同じ人が務める場合が多いのですが、幼い子供が喪主となる場合は金銭的余裕がなく負担するのが難しいものです。 そこで、喪主とは別に施主を指名して費用面でのサポートをおこなうことがあります。 金銭的な負担だけでなく、葬儀の進行などの打ち合わせに参加するなど、喪主を全面的にサポートする役割を担当します。親の遺産で支払う
葬儀にかかる金額が大きいため、親の遺産から支払う方法が採られる場合があります。 この場合、後述しますが相続税の控除対象とできるなどのメリットがあります。相続人で分担して支払う
もし、親の配偶者や兄弟がおらず一人っ子のケースでは、親の葬儀費用は子供一人で負担しなければなりません。 一方で、兄弟がいるケースでは相続人が複数存在するため、喪主の負担を減らすという目的で葬儀費用を分担して支払う場合も多いです。 葬儀費用は、喪主などがひとりで全額支払うなどのルールはなく、相続人同士で話し合い分担する場合も多いです。葬儀でかかった費用の支払い方法は3つ
葬儀を執りおこなって発生した費用について、葬儀社に支払う方法は主に以下3つあります。- 現金での支払い
- クレジットカードでの支払い
- 葬儀ローンを利用しての支払い
現金での支払い
葬儀社に対しての支払い方法として、最も一般的なのが現金での支払いです。 基本的には、指定する銀行口座に費用を振り込む形で支払いますので、現金払いと言っても手渡しで支払うことは稀です。 現金払いの場合、金利などがかからず最もお得に支払いできる可能性が高いメリットがあります。 ただし、数百万円の残高がない場合は現金一括で支払いできない可能性があります。コンビニエンスストアでの支払いに対応している場合もある
現金払いの場合、口座振り込みが基本的な方法となりますが、葬儀の規模が小さく数十万円の費用で済む場合はコンビニエンスストアでの支払いに対応している場合があります。 この場合、いただいた香典を用いてそのまま支払いできるメリットがあります。クレジットカードでの支払い
クレジットカード払いに対応している場合、葬儀費用をクレジットカードで支払うことができます。 通常のショッピング枠の中で、一括だけでなく分割やボーナス払いで支払うことができるメリットがあります。 また、クレジットカードで支払えばクレジットカードのポイントを獲得できる点も魅力的です。 ただし、クレジットカードには利用限度額があり、もし利用限度額を超える費用の場合はクレジットカード払いできません。 ほかにも、分割払いの回数によっては高い利息を負担しなければならず、トータルの支払い費用が高くなる傾向があります。葬儀ローンを利用しての支払い
葬儀費用を現金で支払うのが難しい方のために、葬儀ローンが用意されている場合があります。 葬儀ローンは、信販会社や銀行などが提供しており、意外と多くの商品があります。 葬儀ローンを利用すれば、月々の負担額が少なく葬儀費用を支払うことが可能です。 ただし、ローンである以上審査を受ける必要があり、場合によっては審査落ちして利用できない場合があります。 また、利息が高めであり現金払いよりも高い費用を負担しなければなりません。葬儀の費用を支払う際に注意すること
葬儀の費用を支払う際には、以下の点に注意してください。- トータル費用を意識して支払い方法を選択する
- 葬儀費用は相続税の控除対象となる
- 香典を費用の支払いに充てることもできるが過度に期待しない
- 故人の預金口座が凍結していないかを確認する
トータル費用を意識して支払い方法を選択する
費用の支払い方法として、現金、クレジットカード、葬儀ローンの3つがありますが、現金以外の方法では利息がかかる場合があります。 特にクレジットカードでリボ払いを選択した場合、15%などの高い利息を負担しなければならず、トータルの支払い費用が大きく異なります。 手元にまとまった現金がない場合に利用できる反面、トータル費用も意識して支払い方法を選択してください。葬儀費用は相続税の控除対象となる
被相続人が亡くなられて葬儀を執りおこなう場合、社会通念上当たり前におこなわれることとされていることから、葬儀費用は必要な経費となり相続財産から差し引くことが可能です。 葬儀にかかる費用は一般的に200万円程度となりますが、相続税の税率では10%が最も低いものの、概ね20万円程度の税負担が軽減できるのです。 なお、国税庁では以下の費用を葬儀費用として計上できるとされています。葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行った時にはその両方にかかった費用が認められます) 遺体や遺骨の回送にかかった費用 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(たとえば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用 引用:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用必要なものがあれば、確実に計上して節税に繋げましょう。
香典を費用の支払いに充てることもできるが過度に期待しない
葬儀の際にいただける香典については、葬儀用に充てても問題ありません。 ただし、香典だけで葬儀費用を全てまかなうのは困難であり、その理由として香典は半返しが基本的であるためです。 よって、自己負担することを覚悟して資金を用意するようにしましょう。故人の預金口座が凍結していないかを確認する
葬儀費用を、故人の口座から支払いたい場合があります。 ただし、故人の預金口座については通常は相続人や親族から銀行に死亡の連絡を受けた時点で時点で凍結されます。 もし、凍結されてしまっている状態では以下の手続きにより費用を引き出す必要があるのです。- 預金の仮払い制度を利用する
- 預金だけ先に遺産分割協議をおこなう
葬儀費用を負担できない場合の対処法
もし、葬儀費用を負担することが難しい場合、以下のようなケースで対処法があります。- 公的健康保険に加入しているケース
- 社会保険に加入しているケース
- 生活保護を受給しているケース