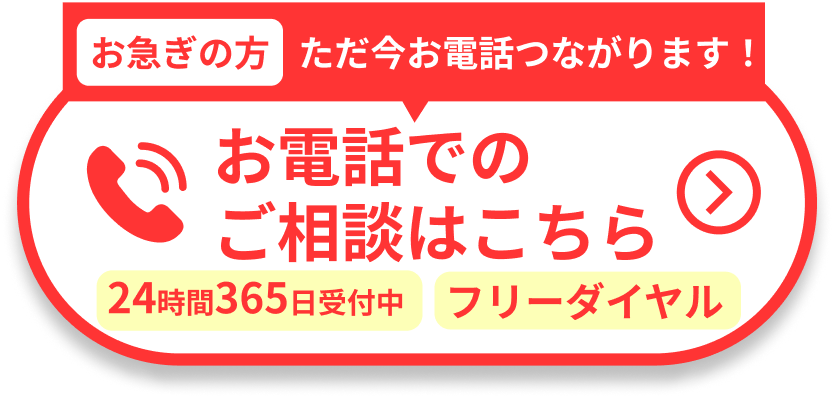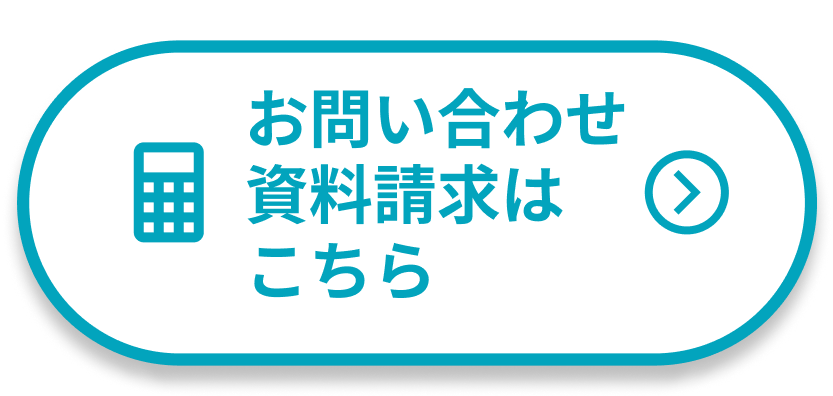目次
遺品整理とは?
遺品整理について改めて説明すると、故人が生前使用していたものや想い出の品と言った、故人が残された品物となる遺品を整理する行為を指します。 遺品とは、家財道具や衣類、写真、手紙、通帳、財産価値のある品など、広範囲にわたるのが特徴です。 遺品は、そのままの状態で残すことによって、それを見る度に故人の思い出が蘇ってしまい、心が重くなりがちです。 また、遺品がそのまま放置されていると傷んだりスペースが取られたりするため、遺品整理は必要となります。 故人の私物を整理する行為は、故人が生きていた証となるものと改めて向き合う必要があり、残された家族が再び悲しみや寂しさに包まれてしまいがちですが、それを乗り越えて遺品整理はおこなうべき行動となっています。 遺品整理をはじめるにあたって、まずは故人が遺言やエンディングノートが存在するのかをよく確認してください。 故人が、遺言やエンディングノートに遺品に関する事柄を残していれば、それを最優先として考える必要があります。 そして、実際に遺品を残す、残さないを判断していくことになりますが、作業スペースを事前に確保しておくと効率よく作業を進められるのでおすすめです。 残すべき遺品としては、以下のようなものが存在します。- 遺言書
- エンディングノート
- クレジットカード
- 身分証明書
- スマートフォン
- 写真
- 思い出の品
- レンタル品
- 通帳
- 印鑑
- 貴重品
- 鍵
- 市場価値のあるもの(貴金属など)
- 廃棄処分する
- 業者に買取ってもらう
- リサイクルする
- フリマアプリやネットオークションなどで売却する
- 寄付する
- 形見分けする
遺品整理を行う時期は?
遺品整理を実施しるタイミングについては、特に正式な決まりごとはありません。 一般的には、以下のタイミングで実施することが多いです。- 法事に合わせる
- 葬儀後の手続きに合わせる
法事に合わせる
遺品整理をおこなう一般的なタイミングとしては、以下のような法事のタイミングです。- 四十九日後
- 一周忌
- 三回忌
- 七回忌
- 葬儀後
葬儀後の手続きに合わせる
葬儀を執りおこなう前の段階として、死亡届の提出や埋火葬許可証の交付申請に対応しなければなりません。 また、葬儀が終わった後にも、以下のような手続きが必要となるのです。- 葬祭費や埋葬費の支給申請
- 健康保険の資格喪失や資格取得
- 介護保険料過誤納還付金の請求
- 年金受給権者死亡届(報告書)の提出
- 遺族基礎年金や遺族厚生年金の請求
- 健康保険の資格喪失や資格取得
- 免許証やパスポート等の返納
- 公共料金等の手続き
- 雇用保険受給資格者証の返還
遺品整理の方法は?
遺品整理を進めるにあたって、主に以下2つの方法で進めることができます。- 遺族で協力して行う
- 遺品整理業者に依頼する
遺族で協力して行う
遺品整理は、先に紹介したとおり一人で対応するのはまず不可能です。 また、自身が高齢な場合は体力的な衰えによって思うように作業できないケースも多いです。 そこで、遺族と協力しながら作業すれば、短期間で効率よく作業をおこなえます。 安全性という観点でも、重いものを複数人で持てば事故を防止できる可能性があります。 さらには、自分ひとりで進めるのではなく遺族の意見を聞きつつ仕分け作業ができるため、後々トラブルに発展するリスクを低減可能です。遺品整理業者に依頼する
遺品整理は、身内だけでなく業者にも依頼可能です。 多くの遺品整理業者が存在しており、遺品整理業者に依頼すれば自分で作業することなく遺品整理が完了します。 当然、遺品整理業者を利用するにあたって費用がかかりますが、費用対効果を考えればお得になる場合もあります。 遺品整理業者では、遺品の仕分けから不要と判断したものの処分、そしてオプションで清掃などにも対応してもらえる点が魅力的です 遺品整理業者によっては、不用品を買い取ってもらえる場合もあり、買取費用を遺品整理費用に補填することも可能です。 ただし、遺品整理業者によっては依頼者の意向を無視して遺品を仕分ける場合があります。 また、処分する遺品を不法投棄するなどのトラブルを発生させるリスクもあるため、業者選びは慎重におこなう必要があります。遺品整理を行う際の注意点
遺品整理をおこなうにあたって、注意すべきポイントがあります。 特に、以下の点に注意して遺品整理を進めてください。- 書類の処理
- 親族とのトラブル