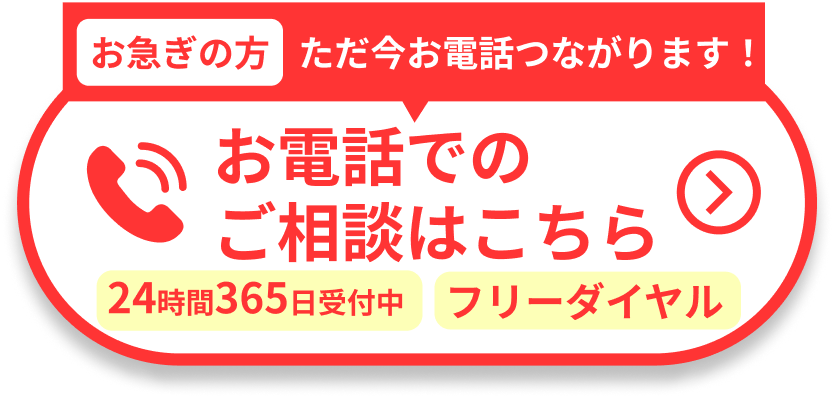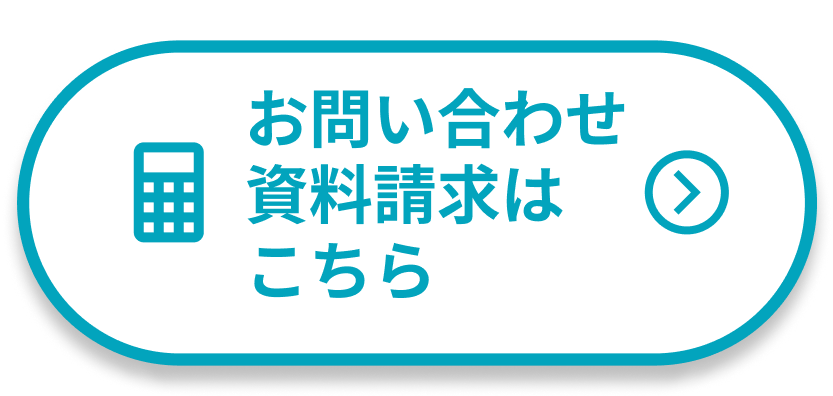目次
玉串奉奠とは?
始めに、玉串について紹介すると神道の儀式において使用される、榊などの常緑樹に紙垂を装飾したものを指します。 紙垂とは、その名のとおり紙を使用することが多いですが、古くは木綿が使用されていた時代が長く続きました。 神社にお参りするときに、普通に参拝するケースと神職に祝詞をあげたり、祈祷・お払いしてもらう際に正式参拝したりするケースがあります。 玉串は、上記のケースで言えば正式参拝する場合に神様への捧げものとして祭壇に奉納する形です。 この、玉串を奉納する行為のことを玉串奉奠と呼ぶのです。 なお、「奉奠」を「奉天」と記載してしまうケースが多いですが、これは誤りですので注意してください。 玉串奉奠は、主に以下のようなシーンでおこなわれています。- 結婚式・安産祈願・お宮参り・七五三などで祝詞を奏上してもらう場合
- 地鎮祭などの神事
- 神道の葬儀や法要の際に焼香の代わりにおこなう
玉串奉奠の意味は?
玉串には、神前のお供えものとして、ほかの米や酒、塩、水といった神饌と同じ意味合いを持つことで知られています。 ただし、神饌と玉串が相違する点としては、玉串の場合は玉串奉奠という形でお供物として参列者が捧げて祭壇に拝礼する点です。 玉串の歴史としては、古くは古事記の天の岩戸の隠れの神話に始まったとされています。 古事記では、天照大御神の岩戸隠れの祭をおこなう際に、神々がおこなった祀りでは真榊に玉や鏡などをかけ、天照大御神の出御を仰いだという記録があります。 名前の由来は諸説あるものの、江戸時代の国学者である本居宣長氏によれば、神前に手向けるという理由によって「手向串」という形で、供物の意味であるとしています。玉串奉奠の手順
葬儀の場において玉串奉奠をおこなう手順としては、まず席を立ち祭壇へ近づく前に、斎主から玉串を受け取ります。 なお、受け取る際に斎主へ一礼し、渡された榊の枝を両手で持ってください。 また、細かな持ち方にも決まりがあり、右手で枝の根元を摘まむ形で持ち、左手は枝先を下から支えて持ってください。 また、左手は右手よりも高い位置をキープする必要があります。 この持ち方をキープしたまま、玉串を乗せる机となる玉串案へ近づいて、一礼した後に玉串を捧げます。 ここで、玉串が祭壇から見た場合に正位置になるようにしなければなりません。 玉串を手で持ったまま、両腕を胸元あたりの高さに上げて、玉串を持つ両手の位置を逆に持ち替えてください。 持ち替えた状態のまま、枝の根元が祭壇へ向くような形で、右手を引き時計回りに玉串を回転させます。 そして、正しい向きにしたら玉串案へ静かに玉串を置いて、数歩下がります。 その後、2回90度程度お辞儀して、二回偲び手をおこない、90度のお辞儀を一回してから軽く一礼して祭壇から離れてください。 この際に、遺族へ会釈してから席へ戻りましょう。 また、葬儀となりますので拍手などは音を立てないようにおこなうのがマナーです。仏式との違い
神式の葬儀と仏式の葬儀においては、信仰する宗教の違いがあるため進行が微妙に異なります。 また、基本的な考え方にも大きな違いがあるのです。 代表的な違いとしては、死生観に対する考え方が挙げられます。 仏式の場合は、故人は生まれ変わるという輪廻転生の考え方に基づき、故人は死後冥界へ旅立つと考えられています。 よって、仏式の葬儀においては僧侶が故人を極楽浄土へと導くための行為として、読経や焼香をおこなっているのです。 一方で、神式においては故人は死後すぐに家の守り神となるという考えがあります。 よって、死後の世界に導くためにおこなう焼香ではなく、玉串を神前に捧げる行為をおこない、これが玉串奉奠となります。玉串奉奠で注意したいマナー
玉串奉奠をおこなう際には、以下のようなマナーを遵守しなければなりません。- 玉串料と初穂料の違いに注意する
- 神道では数珠を使用しない
- 神式の不祝儀袋は蓮の絵が入っていないものを使用する
- 服装は特に決まりがないが黒を基調としたものを身につける