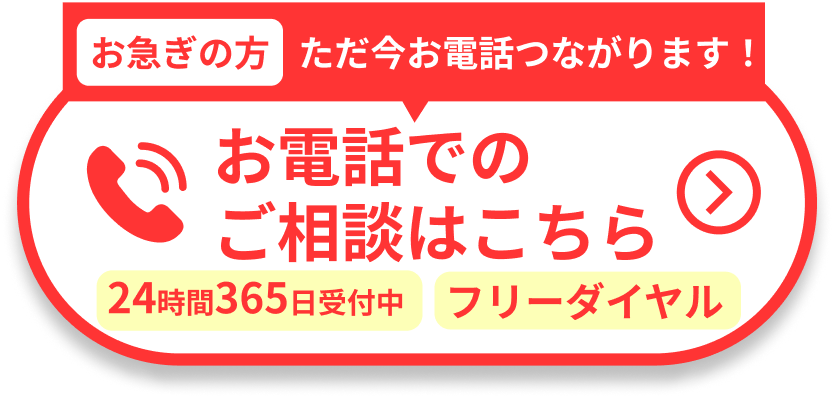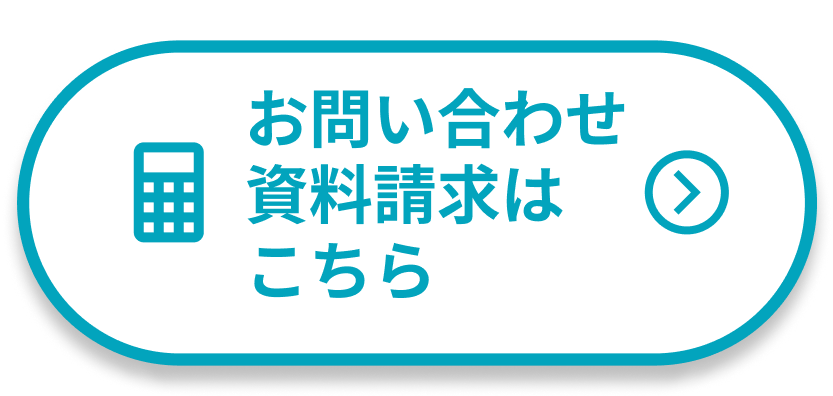目次
葬儀で渡すお布施の金額
お布施とは、葬儀や法要の際にお坊さんに対してお礼として渡すお金のことを指します。 現代社会において、お布施を坊さんにお金を渡す行為は当たり前になっています。 実は、歴史を紐解くと金銭だけでなく以下のようなものを渡していたのです。- 家にある反物や骨董品
- 収穫したお米
- 財施:自分のお金や品々を分け与える
- 法施:仏の教えを惜しみなく人々に施す
- 無畏施:人々が苦しんで不安な気持ちを抱えている際に相談にのってよい方向に導く
相場や目安について
お布施の金額については、葬儀の儀式や法要ごとで相場が異なります。 さらに、宗派や地域によっても異なりますが、大まかな相場は決まっています。 葬儀の場合は、地域や菩提寺との関係性によって異なるものの、全国平均で15万円から50万円の連費が相場です。 葬儀では以下がおこなわれますが、そこでお坊さんがお経をおこないます。- 通夜:夜通しで故人との別れを惜しむ儀式
- 葬儀:故人の冥福を祈り別れを告げる儀式
- 告別式:葬儀後に取りおこなわれる最後のお別れの儀式
- 四十九日:3万円から5万円程度
- 一周忌:3万円から5万円程度
- 三回忌:1万円から5万円程度
- 七回忌:1万円から5万円程度
NGな金額とは?
お布施を渡す際に、少ないと失礼に当たるイメージがあります。 また、各種お祝いを渡す場合、金額が高すぎても相手に気を遣わせるものです。 そこで気になるのが、お布施において不適切な金額があるかどうかですが、実際にNGとなる金額はありません。 気持ちを伝えるものであり、あくまでも相場を見つつ適切な金額をお渡しする必要があります。 なお、結婚式やお香典において偶数にならないようにするという決まりがありますが、お布施には該当しません。 一般的に不吉とされている金額をお渡ししてもマナー違反にはならないものの、あまりに中途半端な金額にならないように、可能な限り調整してください。お布施を渡す時のマナー
お坊さんにお布施を渡す際には、マナーを順守しないと失礼に当たるので注意が必要です。 ここでは、お布施を渡す際のタイミングとマナーについて解説します。タイミングについて
お布施を渡すタイミングは、葬儀と法事、法要でそれぞれ異なります。 各儀式別のお布施を渡すタイミングは、以下のとおりです。葬儀のタイミング
葬儀にお坊さんを招く際に、お布施を渡すタイミングとして儀式前の段階が最適です。 儀式が始まるまでの間に、喪主や遺族とお坊さんが顔を合わせる機会があります。 葬儀をお願いするタイミングともなるため、お布施も同時に渡すのが無難です。 なお、葬儀会社を経由して依頼しているケースでは、顔合わせの時間を設けてくれる場合が多いです。 足を運んでもらったことに対して、「本日はよろしくお願いいたします」や「本日は故人の供養のためにお越しいただきありがとうございます」などとあいさつの言葉をかけると同時に、感謝の気持ちを込めお布施も手渡しましょう。 なお、儀式開始前に渡す余裕がない場合は、一連の儀式を執りおこなった後に渡しても問題ありません。 僧侶が式場を離れると手渡しするきっかけがなくなるため、儀式が終わってから帰宅されるまでの間に時間を設定してください。 なお、お坊さんに手渡す際には直接手渡しせず、小さなお盆に載せたり袱紗の上に置いて渡してください。 また、お坊さんが文字が読めるように封筒の向きを変える配慮も必要です。法事のタイミング
法要の場合でも、儀式が始まる前にあいさつをする時間を設定している場合、そのタイミングでお布施を手渡すのが一般的です。 なお、合同で儀式を執りおこなう場合は、あいさつする時間が十分に設定できない可能性があります。 この場合は、儀式を執りおこなう前の受付口で渡すのが一般的です。 ただし、僧侶に直接手渡しできないため、受付の担当者にお渡しします。 儀式前に渡せるタイミングがない場合、儀式が終了した後に直接手渡します。 なお、多くの参列者でごった返す可能性がある場合は、状況が落ち着いた後に渡してください。 この際には、お礼の言葉も忘れずに添えましょう。マナーについて
お布施を渡す際には、そのままお金を手渡しするのは無礼です。 奉書紙または封筒に入れて、手渡しするのが一般的となっています。 また、奉書紙または封筒の表と裏、そして中袋には以下のように文字を記載してください。お布施の表書き
お布施の表面正面中央上部には、縦書きで「御布施」と記入してください。 市販のお布施袋にはすでに文字が印刷されているケースがありますが、その場合は記入の必要はありません。 もし、お布施以外にも交通費として御車料や宴席代として御膳料を渡す場合には、同じ箇所に「御車料」と「御膳料」と記入してください。 袋の下部には喪主の名前を記載することになりますが、以下のパターンで記載します。| 記載パターン | 記載内容 |
| 名字のみ | 表書きに名字のみ記入しても問題ないが、裏面には氏名(フルネーム)と住所、電話番号を忘れずに記入しなければならない。初めて葬儀等をお願いする僧侶の場合、フルネームで記入するのがベター。 |
| 氏名(フルネーム) | 喪主の氏名をフルネームで表面に記入すると、裏面に記入すべき住所や名前を省略可能。初めてお願いする僧侶の場合、裏面にも住所や電話番号などを記入するのがベター。 |
| ○○家 | 「○○(家名)+家」と記入する。表面に家名を記入する場合は、裏面に喪主の氏名をフルネームで記入しなければならない。 |
お布施の裏書き
奉書紙と中袋を使用せず、白い封筒でお渡しする場合、裏面に金額や喪主の氏名などを記入してください。 通常、右上に金額、左下に氏名や住所などを縦書きで記入するのが一般的です。 住所の番地などの数字は漢数字を用いて表記し、金額を記入するときには旧漢数字を使用してください。 表書きに名字のみを記入した場合、裏面に氏名(フルネーム)を記入するのが無難です。 また、初めて依頼する僧侶の場合は電話番号も記入するとよいでしょう。お布施の中袋
中袋とは、お布施の紙幣を入れるための袋を指します。 中袋の表面中央に、お布施する金額を旧漢数字で記入してください。 例えば、10万円をお渡しする場合は、「金拾万圓也」と記入します。 中袋の裏面には、以下の項目を漏れなく記入してください。- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- 氏名