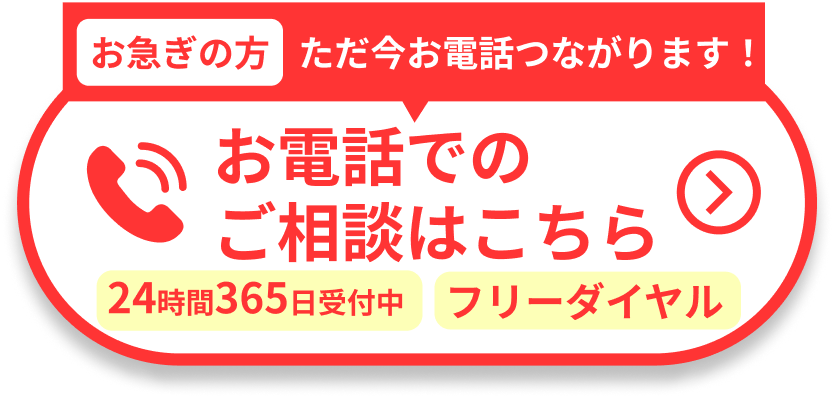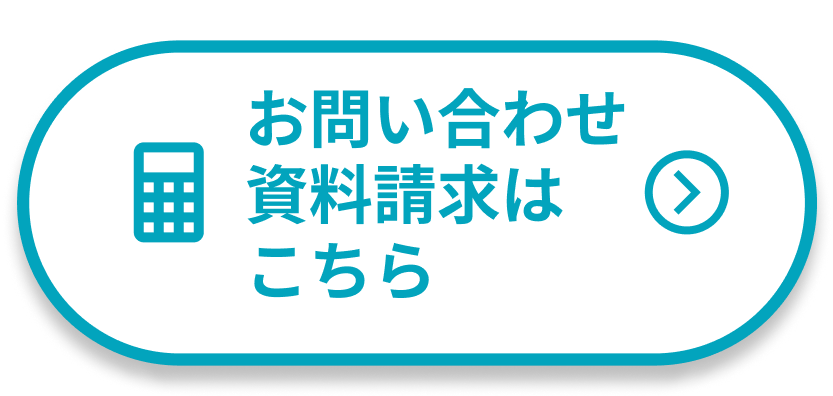目次
死亡届とは?
死亡届とは、人が亡くなったことを法的に証明するための書類となります。 戸籍法の第86条と第87条で、死亡届の届出の期間や書類、届出人などが細かく規定されています。 死亡届は、死亡した事実を役所や保険会社などに対して通知する意味合いがあり、死亡後の様々な手続きにおいて重要な資料です。 例えば、死亡保険をかけていた場合、実は亡くなっていないのに保険金が支払われたら大問題となります。 そこで、公的な文書として死亡届を作成した上で提出して、本当に亡くなったことを証明しなければなりません。 死亡届は役所で入手でき、また自治体によってはホームページで様式をダウンロードできる場合もあるので、よく確認してください。 死亡届は、用紙がA3サイズで左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。 病院で亡くなった場合、医師から右半分の死亡診断書を記入され手渡される場合が大半です。 また、事件などに巻き込まれて亡くなった場合、警察が死体検案書を記入して手渡されます。 よって、基本的には自分で死体検案書を記入することはありません。 自分で記入が必要な部分は左半分の死亡届の箇所のみとなり、以下の項目を記入してください。| 記入項目 | 詳細 |
| 提出日 | 窓口に死亡届を提出する日を記入する。死亡届の提出には期限があり、正当な理由なしに届け出期日を超過すると戸籍法により3万円以下の過料を徴収されるので注意する。 |
| 死亡した時と場所 | 死亡した時と場所を死亡診断書(死体検案書)を参考に記入する。死亡診断書が記載されていない場合は空欄としておき、後から記入してもよい。 |
| 死亡した方の住所と世帯主の氏名 | 死亡した方が住民登録している住所と世帯主名を記入する。世帯主が亡くなった場合は、亡くなった方の氏名を記入する。 |
| 死亡した方の本籍の記入 | 本籍地が記載されている住民票を取得するなどにより、本籍地を確認した上で記載する。 |
| 死亡した時の世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業 | 死亡した時の世帯のおもな仕事について、該当するものにレ点チェックを入れる。死亡した人の職業・産業は国勢調査のための欄であり、任意で記入する。 |
| 届出人の住所・本籍・署名など | 届出人の該当する箇所にレ点を入れて、必要事項を記入する。押印が必要となる箇所があるため、忘れずに押印する。 |
- 火葬をする火葬場の名前
- 届出人欄に記載した人と死亡者との関係
死亡届の提出先について
死亡届を作成するだけでは、当然意味がありません。 役所に提出の上で受理されて初めて意味がありますが、では死亡届はどこに提出すればよいのでしょうか。 ここでは、死亡届の提出先などについて解説します。いつまでに必要?
先に紹介したとおり、死亡届には届出期限が設定されています。 戸籍法で定められており、死亡の事実を届出義務者が知ってタイミングから7日以内に提出しなければなりません。 例えば、1月1日に死亡して死亡を知った日が1月2日であった場合、1月2日から7日以内であるため1月8日が提出期限です。 なお、上記は国内でなくなった場合の期限であり、もし海外でなくなった場合はまた異なります。 海外で亡くなった場合の届出期間は、死亡の事実を届出義務者が把握してから3カ月以内です。 日程的に余裕があるように見えますが、他に実施しなければならない手続きもあるので、余裕をもって早めに対応してください。 なお、国内国外問わず期間内に届出できなかった場合は、届出義務者には5万円以下の過料を徴収されます。必要な書類について
死亡届の提出時に必要となるものとして、以下があります。- 死亡届書
- 死亡診断書または死亡検案書
- 印鑑
届出を提出できる人は?
死亡届を提出する義務がある人はルール上決まっており、以下3つの段階があります。- 同居する親族
- 親族以外の同居人
- 家主や地主、家屋・土地などの管理人
- 同居していない親族
- 後見人
- 補佐人
- 補助人
- 任意後見人
死亡届の提出方法
死亡届の実際の提出までの流れとしては、以下のようなステップでおこなわれます。- 死亡診断書の交付を受ける
- 死亡届の部分を記入する
- 届書・死亡診断書を提出する
- 火葬許可証を受領する
死亡診断書の交付を受ける
死亡診断書とは、人が死亡したことについて、医学的や法的な観点で証明するものを指します。 死亡診断書では、どのような状況で亡くなられたのかを、医師が検案した後で不審な点がない場合に交付されるものです。 死亡診断書がないと、もし亡くなった状態でも死亡していると認められないため注意してください。 死亡診断書は誰でも作成できるものではなく、医師または歯科医師だけが作成可能です。 亡くなる24時間以内に診察しているケースを除けば、必ず医師が直接死亡を確認した上で作成しなければなりません。 ただし、一定の条件を満たしているケースでは、医師が対面していない状態であっても看護師が死亡診断を代筆したり交付したりすることができます。死亡届の部分を記入する
先に紹介したとおり、自分で死亡届の部分に必要事項を記入してください。届書と死亡診断書を提出する
必要な書類の記入が完了したら、死亡届を提出します。 死亡届と死亡診断書の提出先は、以下のうちいずれかが所在する役所となります。- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地
火葬許可証を受領する
火葬許可証とは、市区町村役場において発行されている、亡くなられた方の遺体を火葬することを許可した事実を証明する書類のことです。 日本の法律においては、火葬することが義務付けられていませんが、9割以上が火葬を選択しています。 火葬については、期限は定められていないものの、大半のケースで葬儀の日に火葬を同時におこなう形が取られています。 よって、火葬許可申請書は死亡届と同時に提出する形が一般的です。 火葬許可申請書は、市区町村役場の窓口に対して死亡届を提出するタイミングと同時に、火葬(埋葬)許可申請書を提出して手続きします。 火葬許可申請書では、以下のような内容を記入しなければなりません。- 故人の本籍地
- 現住所
- 火葬場の情報など
死亡届の保管方法は?
死亡診断書の場合、死亡届と共に提出するため原本は手元に残りません。 死亡診断書は携帯電話の解約や保険金の請求などで使用するため、事前にコピーをとって各手続きが終わるまで保管してください。 なお、死亡証明書の期限については、死亡届を提出した役所によって変動します。 提出先が故人の本籍地の市区役所町村役場の場合は、死亡届を提出してから約1カ月以内は届けを出した市区町村役場で受け取り可能です。 1カ月以上経過すれば、死亡届は本籍地を管轄する法務局に移管され法務局へ請求しますが、法務局での保存期間は27年間となります。 提出先が故人の本籍地以外の市区町村役場に死亡届を出した場合、死亡届を提出してから約1年間は、届けを出した市区役所町村役場で請求可能です。 1年以上経過した場合は、死亡届は本籍地を管轄する法務局に移管されるため、法務局へ請求してください。死亡届を提出しないとどうなるのか
死亡届を期限内に提出しないと、届出義務者には5万円以下の過料が課されます。 同時に、以下のような影響を及ぼします。- 年金受給に影響する
- 世帯主の変更ができない
年金受給に影響する
死亡届の提出期限を過ぎると、亡くなった方の年金支払いの停止手続きが不可能となります。 死亡届を提出した後、早急に最寄りの年金事務所や相談センターに年金受給の停止を申請しない限り、亡くなった方の年金は停止できません。 亡くなった方が、厚生年金を受給していたか、また国民年金を受給していたによって、申請期限が変動するため確認が必要となるのです。 具体的には、以下のような期限の違いがあります。- 厚生年金の場合:死亡してから10日以内
- 国民年金の場合:死亡してから14日以内