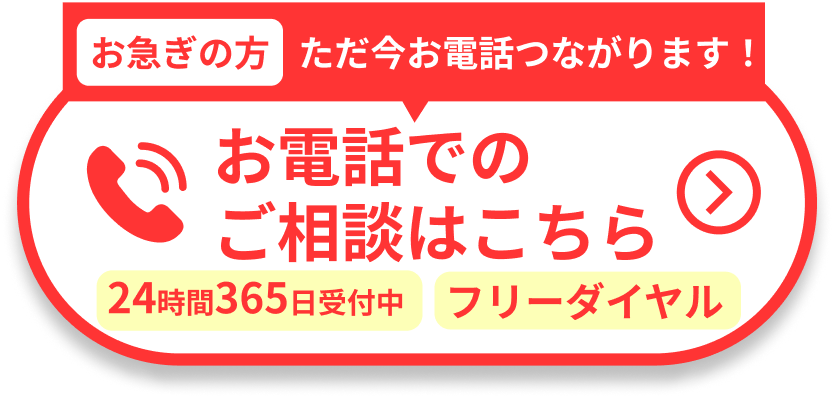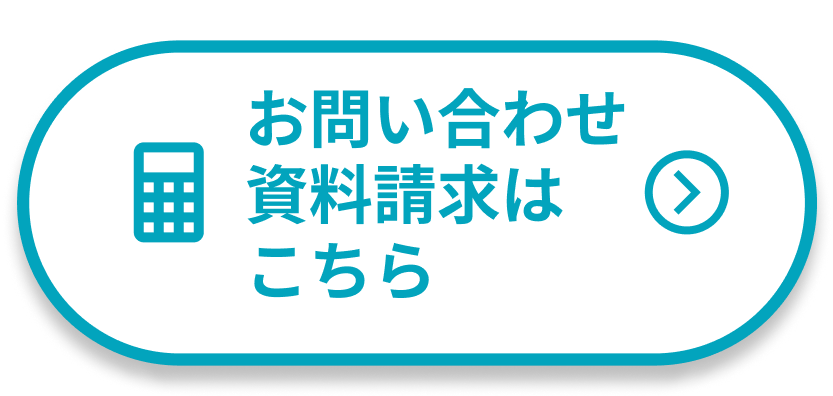目次
訃報とは
訃報とは、人が亡くなったことを知らせることをさします。 なお、訃報は「ふほう」と呼び、「けいほう」や「とほう」ではありませんので注意してください。 訃報の「訃」という漢字には、人の死に関することを意味しています。 訃報と似た言葉の1つに「悲報」があり、訃報の類義語として認識されている場合が多いです。 ただし、悲報には「悲しい知らせ」という意味があり、訃報とは似ているようで実は異なる意味があります。 よって、誤って使用しないように注意しましょう。訃報連絡の手段
訃報を伝える手段としては、主に以下4つがあります。- 電話
- 電子メールやSNS
- 手紙やFAX
- 死亡広告や回覧板
電話
電話は、訃報を伝えるために最も相手に伝わりやすい手段です。 他の方法では、実際に訃報が伝わったかどうかを把握しにくいものですが、電話の場合は相手に直接伝えられるメリットがあります。 逝去された後は精神的につらい状況で、伝えたいことを全て伝えられない可能性があります。 よって、事前にどのようなことを伝える必要があるのかをメモして、確実に伝える対応が必要です。 また、相手とタイミングが合わないとなかなか電話がつながらず、また一斉に一人ひとりに対応しなければなりません。 ただし、古くから電話による訃報連絡が一般的な手段となり、失礼に当たらない方法となります。電子メールやSNS
電子メールやSNSツールを使用して、訃報を伝える方法があります。 電子メールやSNSの場合、しっかりと文面を確認した上で訃報連絡できるので、伝え漏れる可能性は低いメリットがあります。 また、多くの方に一斉に連絡できる点も魅力的です。 ただし、一般的に電子メールやSNSによる訃報連絡は目下の人に対して実施する認識が強く、目上の方や近親者に対して適切な連絡方法ではありません。手紙やFAX
手紙やFAXの手段で訃報連絡すると、電子メールやSNS同様に伝えたいことを確実に伝えられるメリットがあります。 また、文面で残ることで高齢者に対して確実に伝えられる点も魅力的です。 他にも、大勢の方に対して死亡通知状の形で葬儀日時も含めて連絡できます。 ただし、手紙の場合は到着するまでの時間がかかってしまう点がデメリットとなります。死亡広告や回覧板
お住まいの地域によっては、新聞の訃報欄に氏名と年齢、葬儀の日時などを掲載してもらえる場合があります。 また、回覧板や掲示板に訃報情報を掲載できるケースもあります。 上記方法で、個別に訃報連絡しなくても逝去したことを伝えることが可能です。 ただし、確実に伝わるかの確証がなく、もし連絡先が不明な方がいて訃報連絡できない際の伝達手段として活用されています。訃報連絡で伝えること
訃報連絡と一概に言っても実は以下2つのパターンがあります。- 亡くなった事実のみを伝える方法
- 葬儀連絡などを含めて伝える方法
- 自身と故人との関係性
- 誰がいつ亡くなった
- 連絡先について
訃報連絡は誰にすべき?
訃報連絡で難しい問題として、誰にすべきかという点があります。 基本的には、故人と関係があった方すべてに連絡するのが一般的です。 そのなかで、以下の優先順位で訃報連絡をおこなってください。- 家族や親族、近親者
- 葬儀を執りおこなう菩提寺や寺、葬儀社など
- 故人が特に親しい関係であった知人や友人
- 故人の知人、友人、会社や学校などの関係者
- 隣近所や町内会、自治会
ケース別の訃報連絡の文例
訃報連絡については、伝える方法や相手との関係性によって、内容を微妙に変化します。 ここでは、以下のパターン別に訃報連絡する際の例文を紹介します。- 電話で伝えるケース
- メールで伝えるケース
- 会社に伝えるケース
- 友人に伝えるケース
電話で伝えるケース
電話で伝えるケースは、主に関係性が深い家族や親族に対しておこなう場合が該当します。 家族や親族に対して電話で連絡する場合、以下のような形で伝えてください。○○○○(故人の名前)の長男の□□(ご自身の名前)です。 本日、入院治療していた父が○○のため亡くなりました。 遺体は、○○に安置しております。 お通夜とお葬式の日程や場所については、決まり次第ご連絡いたします。 何かありましたら、私に私の携帯電話(番号:090-0000-0000)までご連絡ください。また、関係性によってはもう少し砕けた形で連絡することもできます。 次に、故人の友人や知人に対して、電話で連絡する際には以下のような内容で伝えます。
突然お電話して申し訳ありません。 ○○○○(故人の名前)の長男の□□(ご自身の名前)です。 父が○月○日に永眠いたしました。 生前は父が大変お世話になり、心から感謝申し上げます。そして、葬儀日時を含めて連絡する場合は、以下を含めて連絡してください。
お通夜は○月○日の夕方○時から○○○○(葬儀場の名前)において、 お葬式は翌日○日の午前○時から同じ場所で執り行います。 喪主はわたしが努め、形式は○○(宗教やお葬式の形式)で執り行います。
メールで伝えるケース
メールで伝える場合、件名まで含めてマナーに沿った訃報連絡をおこなってください。メールタイトル:【訃報】○○逝去のお知らせ 兼ねてから入院療養していた父〇〇(故人の氏名)が、○月○日に○○にて〇歳で永眠いたしました。 ここに、生前のご厚誼を深謝し謹んで通知申し上げます。 なお、通夜は○○月○○日に○○にて(葬儀場の名称や住所)○○時より、葬儀は同会場で○○月○○日○○時より、〇〇(宗教やお葬式の形式)で執り行います。 喪主は私○○が努めますので、何かあれば私の携帯電話(090-0000-0000)にご連絡ください。なお、先に紹介したとおり目上の方に対しては、メールではなく電話にて連絡してください。
会社に伝えるケース
会社に伝える場合、先に紹介したとおり代表者のみに伝える形で構いません。 代表者とは、直上司や総務部門の担当者などが該当します。 上司に伝える場合の例文は、以下のとおりです。○○部長 ○○ 様 病気療養中であった母が他界いたしましたので、下記にてお知らせ申し上げます。 死亡者氏名:○○○○(享年〇〇歳) 続柄:実母 死亡日時:○○○○年〇月〇日 〇時〇〇分 また、葬儀参加のため休暇を取得したく存じますので、葬儀に関しても合わせて下記にて記載致します。 通夜:○○○○年〇月〇日 告別式:○○○○年〇月〇日 葬儀場:(葬儀場名と住所) 葬儀場電話番号:0120-456-〇〇〇 なお、故人の遺志により、一般参列、御香典、弔電、御供物などの御厚志につきましては、失礼ながら辞退させていただきます。 恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。単に訃報を伝えるだけでなく、休暇をとり迷惑をかける旨も含めて連絡するようにしましょう。
友人に伝えるケース
故人の友人に訃報をメールで伝える場合、以下のような形で連絡してください。○○ 様 突然のメール、失礼いたします。 ○○の長男である○○です。 母○○はかねてより入院加療中でしたが、去る○○年○月○日に○歳にて永眠いたしました ここに謹んでお知らせ申し上げます。 葬儀は下記の通り執り行います。 通夜:○○○○年〇月〇日 告別式:○○○○年〇月〇日 葬儀場:(葬儀場名と住所) 葬儀場電話番号:0120-456-〇〇〇ある程度面識がある関係である場合、もう少し言葉を足して連絡するのもよいでしょう。