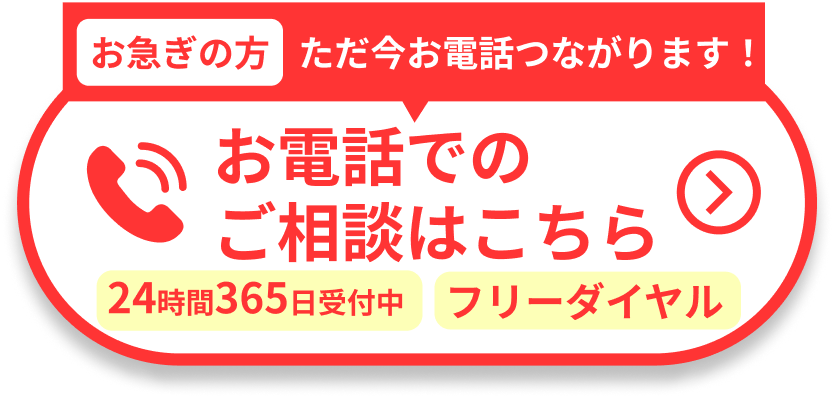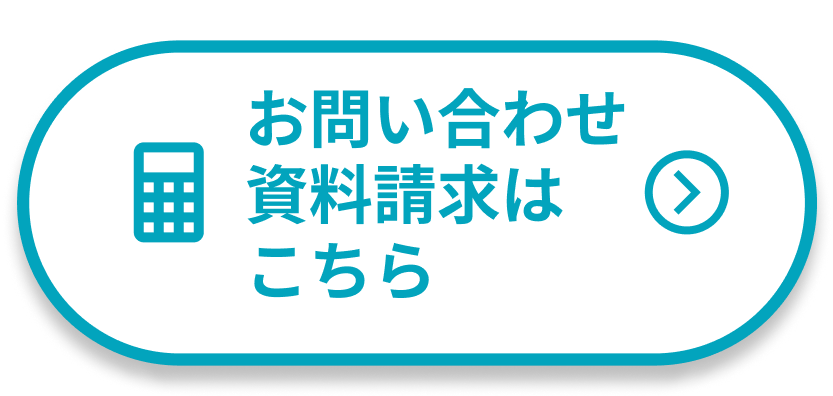目次
お葬式の行われている割合について(家族葬,一日葬,直葬,一般葬)
はじめに、他の方がどのような葬儀を実施しているかを知ることが重要です。 葬儀としては、最近では主に以下4つの方法があります。- 家族葬
- 一日葬
- 直葬
- 一般葬
| 葬儀の形態別割合 | 葬儀形態による増加率 | |
| 一般葬 | 63.0% | 5.4% |
| 家族葬 | 28.4% | 51.1% |
| 直 葬 | 5.5% | 26.2% |
| 一日葬 | 2.8% | 17.1% |
| 社 葬 | 0.3% | 0.3% |
各葬式の費用について(家族葬,一日葬,直葬,一般葬)
家族葬や直葬が増えている背景の1つに、費用面でのメリットがある点が挙げられます。 一般葬の場合、どうしても費用が高くなりがちであり、故人がシンプルな形式の葬儀を望む場合にはあえて一般葬ではなく家族葬や直葬、そして一日葬も視野に入るのです。 では、実際にどの程度費用面での違いがあるかと言えば、以下のような違いがあります。| 費用相場 | |
| 一般葬 | 約149万円 |
| 家族葬 | 約96万円 |
| 直 葬 | 約85万円 |
| 一日葬 | 約44万円 |
各葬式の満足度について(家族葬,一日葬,直葬,一般葬)
葬儀の費用や割合を見てきたところで、実際に葬儀を実施して満足できるかどうかがポイントです。 特に、葬儀は故人にとって最後の花道となり、遺族だけが費用面で満足しても仕方ありません。 いかに、遺族側も参列者側としても満足できる葬儀であったかどうかが鍵となるのです。 その点で、各葬儀の満足度は非常に重要な要素となります。 一般的に、一般葬と家族葬の場合、約75%以上の方が葬儀に満足していると言われています。 むしろ、家族葬の方が満足度が高い状況となっているのが特徴です。 次に満足度が高いのが一日葬であり、それでも70%以上の方が満足されていると回答しています。 一方で、直葬の場合は満足したという方の割合が70%を下回っており、満足できないという方の数も他の葬儀より多くなっています。 以上から、様々な要素を加味してバランスが取れた葬儀としては家族葬が最適と言える状況です。葬儀形式の種類
一言に葬儀といっても、形式や種類はさまざまなものがあります。 以前は宗派による違いが大きいといわれていた葬儀ですが、現在は宗派だけにとらわれるのではなく、故人の意思を尊重した形式が見られます。 どのような葬儀を行うべきか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。 一般的な葬儀形式の種類について見ていきましょう。仏式
仏式は、仏教の宗派に基づき行われている葬儀の形式です。 日本の葬儀では一番多く見られるものになり、仏式を選択する人が少なくありません。 仏教では亡くなった人の魂は極楽浄土に送られると考えられています。 仏式といっても、細かい宗派が存在していますし宗派によってもお経や作法の違いも出てきます。 仏式は、通夜・告別式・火葬を行う点は共通しており、読経やお焼香などの作法を行います。 ただし、地域によっては前火葬で順番が異なる場合もあります。神式
神式は、神葬祭とも呼ばれているもので神道に基づいて葬儀が行われます。 日本の古来の宗教でもあり、八百万の神々という自然界に存在しているものを信仰の対象としています。 神葬祭は、亡くなった人が先祖と共に守り神として祀るための儀式になります。 神式では神社を使うことはほとんどなく、自宅もしくは式場にて行います。 神道では玉串と呼ばれるものを使い、祈りを込めて故人に捧げることで、神様と人間界を繋いでいるといわれています。キリスト教式
キリスト教は、キリストの教えに基づき行われる葬儀形式のことをいいます。 キリスト教では「死」=不幸なものではないと考えています。 そのため、亡くなった人に対してお悔やみの言葉を述べることはしません。 あくまでも、安らかな眠りを祈るための挨拶をします。 また、葬儀の基本的な流れも、通夜を行わずに告別式や火葬のみを行います。 キリスト教式の葬儀では、聖書の朗読を行い讃美歌や献花なども特長になるため、仏式や神式とは作法や儀式にも違いがあります。宗派によるこだわりなし
日本では、宗派について特定のこだわりを持たない人も少なくありません。 葬儀を行うときに特定の宗教ではない葬儀を行うこともあります。 無宗教の場合は、作法に一切の制限がなくオリジナルの葬儀を選択している人もいます。 本格的な葬儀ではなく、故人とのお別れ式のような雰囲気で進んでいくことになります。 なかには、ホテルやレストランなどでお別れ会を行い、思い出の品や写真を流し故人の話をして過ごすこともあります。家族葬について
先に紹介したとおり、満足度が高く費用面でも安く実施できる葬儀として、家族葬に注目が集まっています。 また、新型コロナウイルスの影響もあり、家族葬で葬儀を進めざるを得ない状況が続いている事情もあります。 家族葬の特徴やメリット、デメリットは以下のとおりです。特徴
家族葬とは、故人と親しい関係の方のみが参列して執り行われる葬儀のことです。 家族葬という名称から、家族のみが参列するイメージがありますが、実際にはより幅広い方が参列するのが特徴です。 家族葬に関する明確な定義はなく、どの関係性の方まで参列するのかは主催者の考え方次第となりますが、一般葬と比較して小規模で執り行われることになります。 参列者の違いがあるものの、基本的な葬儀の流れは一般葬と同様です。メリット
家族葬の場合、より一人ひとりの想いが反映しやすいという特長があります。 多くの方が葬儀に関わると、それぞれの方の想いを反映させなければなりません。 同じ方向性の考え方であればまだしも、全く異なる考えをまとめて1つの形にするのは困難です。 そこで、家族葬の場合は一人ひとりの想いを反映させやすく、葬儀をスムーズに準備できるメリットがあります。 また、遺族側としても故人との別れの時間をゆったりと確保できる点も魅力的です。 大規模な葬儀の場合、対応すべき項目が多数に渡り、その対応に追われてあっという間に葬儀が終わってしまう場合が多いです。 故人とのお別れの場でもある葬儀において、少しでも故人に対する思い出などを振り返ってお別れしたいものです。 家族葬の場合、比較的時間的な余裕が生まれるため、よりゆったりと過ごせる点がメリットとなります。 他にも、予め小規模な葬儀が見込まれる場合に家族葬にすれば、一般葬と比較して費用を抑えられます。 さらに、家族葬の場合は形式的なことを省略して、故人の遺志を反映させてより自由な葬儀を執り行える点も魅力的です。デメリット
家族葬のデメリットとしては、参列者が限定されるため、参列者の選択で悩む点です。 例えば、家族に限定すれば全く悩むことなく参列者を限定できます。 一方で、親しい知人などを招く場合、どの範囲まで参列いただくかの判断が難しいものです。 故人が事前にどの範囲まで参列を希望するという表明がある場合は特に困らないものの、特に表明がない場合は遺族が選定しなければなりません。 そこで、故人と親しい関係であったと考えていた方に声がかからなかったなど、トラブルに発展する場合があるのです。 可能な限り、生前の段階で家系図や親しい方との関係をまとめたものがあれば、悩むことなく参列者を選定できます。 また、家族葬の場合は葬儀に関して準備すべき項目が少なく、費用が抑えられるメリットがある反面、葬儀後に対応すべき項目が多いのが難点です。 通常、葬儀が終了した後に遺品整理や各種相続の手続きなどをおこなわなけれなりません。 非常に忙しい最中で、訃報を送ったり、参列できなかった方に対して弔問対応が必要です。どんな人に向いている?
家族葬は、親しい人のみで行う葬儀でもあり比較的自由度が高い方法です。 家族葬が向いている人は以下のようなケースです。 ・宗派にとらわれずに故人の好きなものを取り入れた葬儀にしたい ・落ち着いた雰囲気のなかでオリジナリティのある葬儀にしたい ・親しい近親者のみでアットホームな葬儀にしたい ・葬儀にかける費用を抑えたいと考えている ・参列者の数が少ないため、規模の小さなお葬式を考えている 家族葬は、家族の負担を減らすことにも繋がります。一日葬について
より葬儀内容を厳選して執り行う方法として、年々注目を集めているのが一日葬です。 一日葬の特徴やメリット、デメリットは以下のとおりです。特徴
葬儀の場合、通常は1日目に通夜が執り行われて、2日目に葬儀・告別式の流れで進行します。 一方で、一日葬とはその名の通り一日で葬儀を完了させる葬儀スタイルのことで、具体的には通夜を省略して葬儀・告別式と火葬を一日で執り行う葬儀のことです。 具体的には、以下の流れで合計5時間程度で終了します。- 葬儀告別式:2時間
- 火葬:2時間
- 会食:1時間