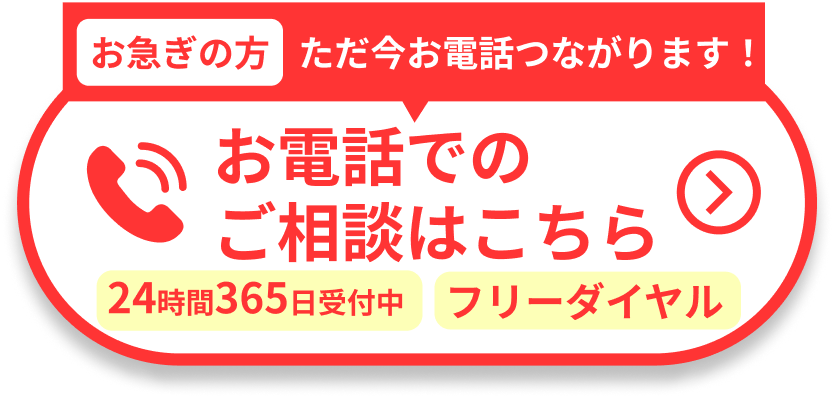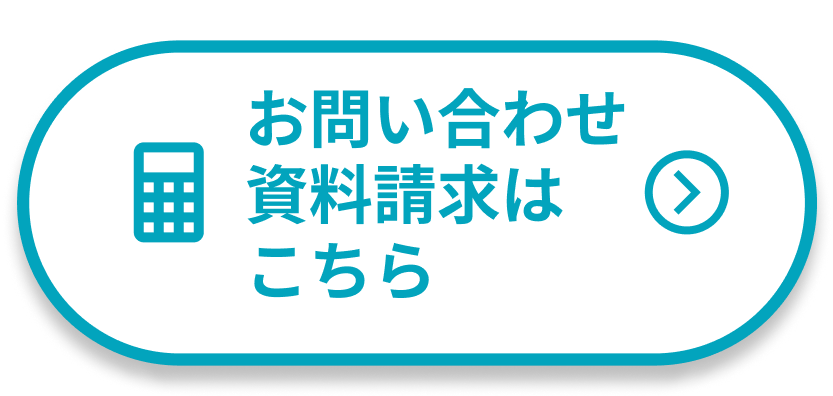目次
亡くなってから葬儀までの流れ?
亡くなってから葬儀までの流れとして、以下のようなステップで進みます。- 家族に連絡
- 業者さんに連絡
- ご遺体の搬送・安置
- 葬儀との打ち合わせ
- 参列者に連絡
- 湯灌・納棺
- 通夜
- 葬儀・告別式
- 出棺
- 火葬・埋葬
家族に連絡
病院などで死亡が確認された場合、即時に死亡診断書が発行され、その後遺体搬送に寝台車の手配をおこなわなければなりません。 同時に、他の家族に連絡する必要があります。 中には、遠くに住む家族もいるため、常に連絡先を確認しておきましょう。 また、危篤状態となった場合など、死期が近い場合はその情報はなるべく展開するのがおすすめです。 それにより、まだ生前の段階で面会でき、生きているうちにお別れできるメリットがあります。 家族だけでなく、親族や親しい知人などにも連絡しておくと良いでしょう。 在宅療養で亡くなられた場合、かかりつけの病院へ早急に連絡してください。 また、かかりつけ病院が存在しない場合、救急車を呼んで判断を仰ぎます。 なお、この際に勝手に遺体を動かしたりせず、医師による死亡確認を待ってください。 他にも、事故死や突然死、自死などにより死去した場合は、医師による死因特定が困難な場合や事故死の場合は、警察への連絡が必要となります。 警察に連絡した後は、検視官や監察医が死因の特定作業をおこない、警察から死体検案書が渡されますが、通常は葬儀社が代行するため、家族としては特段手続きの心配はありません。業者さんに連絡
家族への連絡を取って集合できる方が集合したタイミングで、誰が喪主や施主を担当するかを決定してください。 そして、葬儀形式や参列者の大まかな人数、全体的な予算などについて整合を図ります。 葬儀の規模などについては、遺言やエンディングノート等があれば最大限取り入れてください。 そして、利用する葬儀社を決定する必要があります。 葬儀社を決定したら、すぐに連絡を取り日程や内容を整合してください。 同時に、職場や学校、関係者に対して連絡をおこないます。 死亡届の手続きや供物の手配などは、基本的に葬儀社が請け負ってくれるので、特に自分で対応する必要はありません。 詳細については、葬儀社とよく整合の上で進めてください。ご遺体の搬送・安置
亡くなられた直後、早めに末期の水と呼ばれる行為を実施します。 末期の水とは、茶碗に入れた水と新品の割り箸の先に脱脂綿を巻きつけたものを使用して、故人と血縁が近い人から順番で、脱脂綿を水に浸しての故人の唇を湿らせる行為です。 また、エンゼルケアと呼ばれる遺体に身繕いや死に化粧を実施してください。 通常、亡くなられた方を火葬するまでには、一定の時間を要します。 これは、法律上で死亡直後の火葬は禁止されており、最低でも24時間以上は火葬しないままの状態としなければなりません。 その間、遺体は腐敗等が進行してしまうため、そのまま放置するわけにはいきません。 そこで、亡くなられてから葬儀が執り行われるまでの間に、葬儀場や自宅などで遺体を保管しなければなりません。 遺体を保管することを安置と呼びますが、安置場所まで遺体を搬送する必要があります。 遺体の搬送は、個人でも実施することは可能ですが、法律上で細かなルールがあり、それに従う必要があるのです。 特に、長時間遺体を自動車の中に置いたり、目的地以外の場所に遺体を搬送するのは違法行為です。 意図的ではないにせよ、法律違反を犯すと罪に問われるので注意してください。 そこで、遺体搬送は基本的には葬儀社に依頼するのが一般的となっています。 安置先を決定したら、葬儀社に連絡して搬送を手配してください。葬儀社との打ち合わせ
遺体の安置まで完了した時点で、葬儀社と葬儀に関して具体的な整合を実施します。 依頼したい葬儀内容等は事前に家族内で整合しているため、このタイミングではある程度葬儀社に対して家族の希望を伝える形となります。 最初に葬儀の日程を仮決定してから、葬儀の具体的な内容について話し合います。 主に決定しなければならない内容は、以下のとおりです。- 葬儀の形式(仏式、キリスト式など)
- 葬儀の種類(一般葬、家族葬、一日葬、直葬、火葬式など)
- 予算規模
- 葬儀プラン
- 葬儀を執り行う場所
- 火葬の日時
- 葬儀の演出など