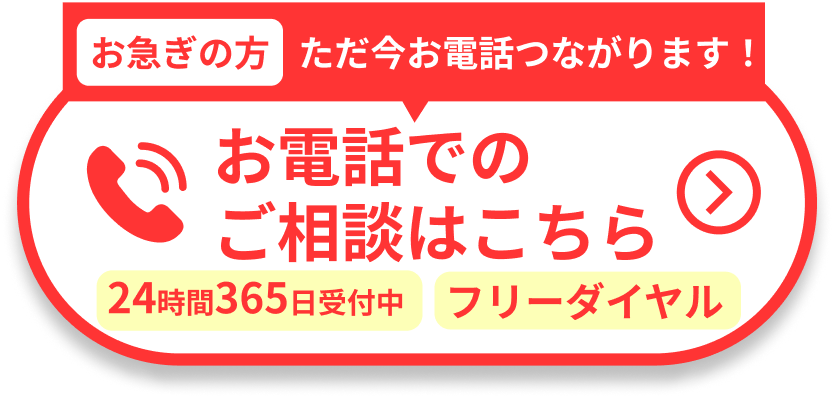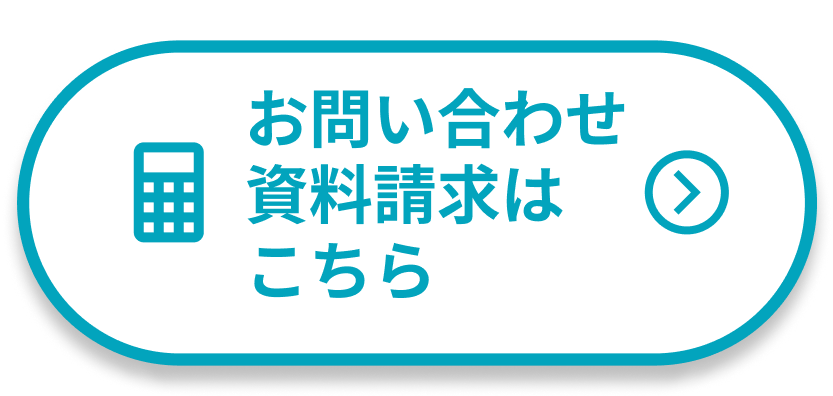目次
無宗教葬儀の特徴は?
無宗教葬儀について改めて解説すると、特定の宗派や宗教において定められた儀式の方法や作法に捉われず、自由なスタイルの葬儀のことです。 無宗教葬儀は自由葬とも呼ばれており、何事にもとらわれずに進める点が特徴となります。 なお。無宗教であっても神仏の存在を否定するわけではなく、無神論ではない点には注意が必要です。 日本では約8,470万人が仏教徒である一方で、無宗教的な思想の人が多いのは事実です。 ただし、無宗教であったとしても神社やお寺を訪問する方が多く、無宗教ではなく無信仰と評されるケースもあります。無宗教葬儀の相場、費用について
無宗教葬儀の場合、後述しますが僧侶などを招かないケースが多いため、仏式葬儀と比較して費用が掛からないケースが多いです。 一方で、仏式葬儀では実施しない内容を無宗教葬儀で実施するケースもあり、一概に費用が安いとは言い切れません。 特に、演出などにこだわりを持つ方が無宗教葬儀を執り行う場合、費用が多くかかりがちです。 また、大前提として無宗教葬儀であっても一般的には式場や火葬場を使用するため、その費用を計上しなければなりません。 以上から、無宗教葬儀の一般的な相場は80万円から160万円程度となります。無宗教葬儀の流れを説明
無宗教葬儀で執り行う場合、主に以下の流れで進行します。- 参列者入場
- 開式の辞
- 黙祷
- 献奏
- 弔電の紹介
- 感謝の言葉
- 献花
- お別れ
- 閉式の辞
- 出棺
- 会食
1.参列者入場
参列者を会場に招き入れます。 参列者が入場される際には、故人が好んでいた曲を流すなどの演出がおこなわれるケースがあります。2.開式の辞
基本的には司会者が、開会の言葉を述べます。 もし、司会者を用意しない場合は喪主が開会の辞を担当するケースが多いです。 開会の辞の事例としては、以下のようなものがあります。皆様、本日は[故人の名前]さんの葬儀に足を運んでいただき、心より感謝申し上げます。今日は特定の宗教的儀式を経ることなく、私たち一人ひとりの心からの敬意と感謝を込めて、[故人の名前]さんの生涯を称える時間といたします。
3.黙祷
仏式の葬儀では、僧侶による読経や参列者からの焼香がおこなわれますが、無宗教葬儀の場合は全員で黙祷を捧げるスタイルを取ります。 黙祷は、声を立てることなく故人に対して心の中で語りかける形で、祈りを捧げる行為です。 黙とうの合図があったら、少し前方に頭を下げて、軽くお辞儀してください。4.献奏
無宗教葬儀において、特徴的な点が献奏です。 献奏とは、元々は神仏に対して音楽を演奏し奉納する行為ですが、故人の霊前などで音楽を演奏して冥福を祈る行為も指します。 無宗教葬儀では、故人の思い出などを振り返る形で献奏がおこなわれるのが一般的です。 スライドや映像などを用いる形が取られ、音楽なども故人が愛したものを使用する形となります。5.弔辞
故人との関係が深い友人などが、弔辞を読み上げます。 一般的には、代表3名程度が弔辞を述べるのが一般的です。6.弔電の紹介
当日参列できなかった方より、事前に送付された弔電を3通程度読み上げます。7.献花
遺族、親族、参列者の順番で、主にカーネーションや百合、菊などを献花します。 献花時は、遺族に一礼して祭壇の方へ進行し、祭壇の前で一礼して実施するのが一般的です。 献花のタイミングで、故人が好んでいた曲などを流すのが一般的となっています。8.閉式の辞
遺族代表として、主に喪主が葬儀の閉式を告げて葬儀が終了します。 閉会の辞の事例としては、以下のような挨拶をおこないます。[故人の名前]さんは、多くの人々に影響を与え、愛された存在でした。彼/彼女の考えや哲学は、特定の宗教や信条に縛られることなく、多くの人々に共感を呼び起こしました。今日の無宗教の葬儀も、その哲学を反映しています。私たちが持っている思い出や教訓を、次の世代に伝えていくことが、最も美しい追悼となるでしょう。
9.会食
葬儀が一通り終了した後、参列者と会食の席を設ける場合があります。 主に、故人との思い出などを語り合う場所として活用されます。無宗教葬儀と仏教の葬儀との違いとは?
無宗教葬儀で気になるのが、仏式葬儀との違いです。 葬儀において、具体的に以下のような違いがあります。- 僧侶を招かず実施する
- 焼香ではなく献花する
- 演出などを自由に設定できる
- 納骨は無宗教の墓地におこなう
僧侶を招かず実施する
無宗教葬儀においては、僧侶を招いて実施しないケースが大半です。 無宗教の葬儀は自由に構築できるため、僧侶に読経をお願いしたり戒名を付けてもらうなどは不要となります。 ただし、僧侶を招くこと自体に特に制限はなく、無宗教葬儀であっても僧侶を依頼して読経をあげてもらうケースがあります。焼香ではなく献花する
焼香とは、仏教において香を焚くことを意味します。 多くの場合、葬儀において細かく砕いた香を摘まんで、落として焚く行為を指します。 焼香自体が仏教における作法となりますが、仏教以外ではカトリックの葬儀でも散香がおこなわれるのです。 一方で、無宗教葬儀の場合はキリスト式葬式やお別れの会などで用いられる、献花を採用するのが一般的です。 また、献花の方法も特に大きな決まりはなく、自由に設定できます。演出などを自由に設定できる
自由葬の場合、特に縛りがなく思い通りの形で葬儀をアレンジできます。 特に、献奏や献花の際には故人の思い出が詰まった音楽や映像などを用いて演出するのが一般的です。納骨は無宗教の墓地におこなう
無宗教葬儀は、お寺を介さず執り行われるため、葬儀の後でお寺のお墓に納骨できません。 もし、先祖代々の菩提寺があっても納骨できないケースが多いです。 そこで、納骨は無宗教の墓地におこなうのが一般的となります。 また、最近では樹木葬や宇宙葬など、より自由な場所に納骨するケースも増えています。無宗教葬儀の葬式のマナーを解説
無宗教葬儀の葬式においても、一定のマナーが存在します。 ここでは、無宗教葬儀の葬式のマナーについて解説します。服装について
無宗教葬儀であっても、服装に関しては一般的な葬儀と同じく喪服で臨んでください。 男性の場合は、黒を基調とした礼服に黒のネクタイを締め、靴下やベルト、靴もダークトーンで統一します。 女性も、黒を基調としたワンピースやアンサンブルなどを基本として、黒のストッキングや靴、バッグで統一してください。 また、派手な化粧などは避けてネックレスはパールを使用します。香典について
香典についても、基本的に仏式葬儀と同様に準備します。 香典袋の表書きには、以下の文字を記載します。- 御霊前
- 御香典
- 御花料
持ち物について
仏式葬儀では数珠を持参しますが、無宗教葬儀では必須ではありません。 もし持参したい場合は、宗教を問わず使用できる略式数珠を選んでください。言葉について
お声がけについても、基本的には一般葬との違いはありません。 「この度はご愁傷様です」や「心からお悔やみ申し上げます」など、遺族に対して思いやりのある言葉を掛けるのが一般的です。 お声がけの際は、以下のような繰り返し言葉や、「四」「九」が付いた言葉の使用は避けてください。- 忌み言葉:死亡、生きている頃、ご存命中、とんだこと、とんでもないこと、めっそうもない
- 重ね言葉:重ね重ね、またまた、たびたび、返す返すも、次々、再び、また、続いて、重ねて、追って