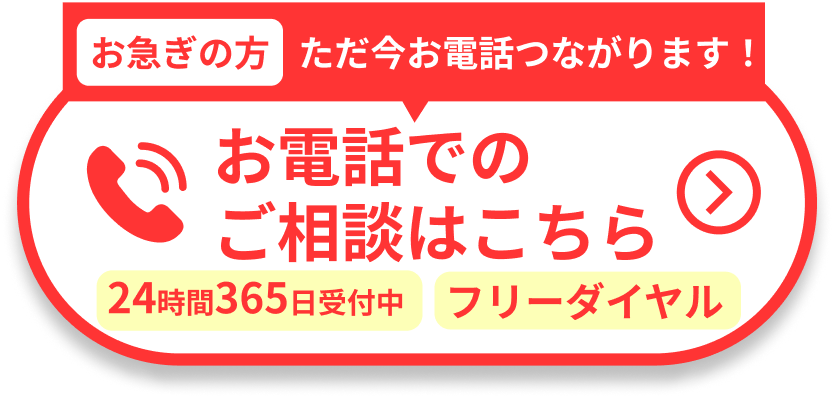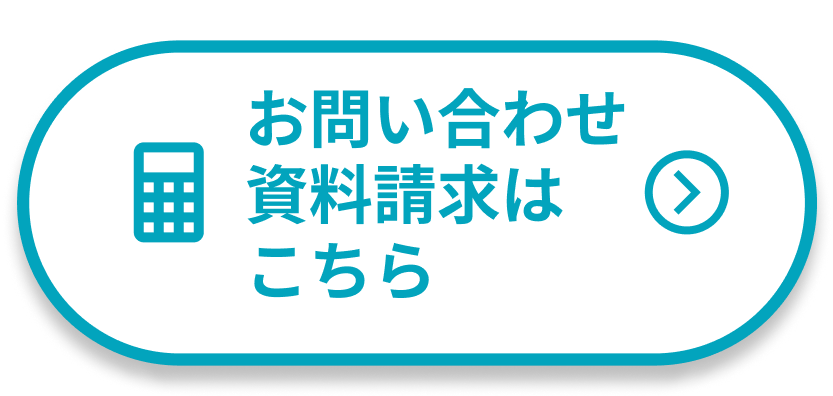目次
仏教葬の特徴は?
仏教葬の特徴は、冒頭でご案内した通り「お坊さんが来て読経を読む」お葬式になります。 本来は「仏教徒」のためのお葬式の形式であり、仏教を信仰している方のためのお葬式です。 同様に、神道を信心している方は神道形式の葬儀「神葬祭」を行いますし、キリスト教を信仰している方は「キリスト教形式の葬儀」を執り行います。 ただし、厳密に言うと日本人の多くは“無宗教”であると言われていますので、「自分が仏教徒」という認識のもと、仏教葬を選択している方はほとんど皆無であるとも言えます。 それなのに多くの方が仏教葬を選択しているのは、どんな理由があるのでしょうか。 それは、多くの方が「それが普通だと思っているから」に他なりません。 また、先祖代々その形式で葬儀を行ってきた、ということも大きな理由となっています。仏教葬の流れを説明
仏教葬の流れは、一般的には次のような流れの儀式になっています。 ※地域の習慣や宗派によって多少内容が異なったり前後する場合があります。 ①一同着席 参列される方は、式場内の椅子席に着席し、静かに開式を待ちます。 参列者は式中に携帯電話やスマートフォンの着信音がならないように、事前に配慮をしておきましょう。 ②導師入場 葬儀を執り行う導師、つまり、お坊さん(僧侶)が入場します。 宗派や地域、そして葬儀の規模によっては、導師だけでなく役僧や脇導師といった役割の僧侶が来て、複数人の僧侶で葬儀を執り行うこともあります。 ③開式の辞 司会者によって葬儀の始まりを告げる開式の言葉が述べられます。 ④読経 僧侶による葬儀の読経が執り行われます。 ⑤弔辞 故人を偲んで友人など近親者からお別れの言葉を述べてもらいます。 なお、近年は家族葬といった小規模な葬儀が多いため、弔辞が読まれることは非常に少なくなっています。 ⑥弔電 主に会社関係や、遠方で葬儀に参列が難しい方などから電報が届く場合があります。 こうして頂いた弔電は、通常司会者が代読して披露します。 ⑦読経 葬儀後半の読経が執り行われます。 多くの宗派では、このタイミングから参列者の焼香が始まります。 ⑧焼香 喪主を先頭に、参列者は順次焼香へと進みます。 通常は親族が最初に行い、次に一般参列者が焼香をします。 ただし、時間の都合上ある程度親族が進んだ所から一般焼香を同時に進めるケースもよくあります。 ⑨導師退室 葬儀の読経が全て終了すると、導師(お坊さん)は退室します。 ※地域や僧侶によっては、閉式の案内が入るまで退室しない場合もあります。 ⑩喪主謝辞 葬儀に参列をして頂いた会葬者に対し、喪主から会葬御礼の挨拶をします。 ⑪閉式の辞 司会者より葬儀式閉式の言葉を述べます。 ⑫お別れ・出棺 棺の蓋を開け、故人との最後の対面・お花手向けをします。 お別れが済むと、蓋を閉め、霊柩車に棺を載せ、火葬場に向けて出棺します。 以上が一般的な仏教葬の流れになりますが、地域や宗派、そしてお坊さんの考え方によっても儀式の順番や内容が異なることがあります。 特に宗派によっては大きく順番が異なることがありますので、上記の流れは参考程度にご覧ください。仏教葬のマナーを解説
仏教葬では、一般的に必要とされるマナーが存在します。 日本で一番多く行われている葬儀形式ですので、あなたも参列する機会があると思います。 ぜひ下記をご覧いただき、参考にしていただければと思います。服装について
通夜・葬儀共に原則は喪服を着用します。 昔は「通夜は華美でない平服で良い」とされていましたが、近年では通夜から喪服で参列する方がほとんどです。 また、礼服については略礼服で済まされるケースが大半で、正装とされる黒喪服(和服)やモーニングを着用することは非常に稀になってきています。 アクセサリーや化粧(マニキュア)は華美にならないように注意し、鞄・靴・ベルト等も黒で統一します。 基本的に毛皮を用いたコート等はNGとされますので、寒い時期の上着なども注意しましょう。 礼服を持っていない子供については、学生であれば学生服が最適とされます。 ただし、特に女子の制服で極端にスカートが短い制服や、あまりにデザインが明るすぎるものについては、「葬儀」という場に相応しいかどうかで判断し、必要があれば略礼服に近い服装にすると良いでしょう。 小学生以下のお子様については、基本的に普段着で構いません。 ただし、あまり華美な色やデザインの服装は避け、紺色・灰色・黒色・白色といった地味な色合いの服装にするように心がけましょう。持ち物について
仏教葬における基本的な持ち物は、①数珠、②香典となります。 ①の数珠は、本来は読んだお経の数を数えるための道具であることから、絶対になくてはならない物ではありませんが、一般マナーとして「葬儀には数珠を持っていく」と定着しているため、持参することが無難でしょう。 焼香の際に左手に持って進みます。 ②のお香典は、故人への供養という意味と相互扶助の考えのもと持参することが一般的となっています。香典について
仏教葬における香典は、宗派によって表書きが異なりますので注意が必要です。 一般的に浄土真宗系(本願寺系)では、表書きを「御仏前」とします。 それ以外の宗派では、基本的に全て「御霊前」と書きます。 ただし、葬儀会場に行くまでどんな宗派か分からない場合も多いので、全て「御霊前」でも問題はなく、失礼にもあたりません。言葉について
仏教葬に限らず、日本のお葬式では「忌み言葉」と呼ばれる言葉を避けることがマナーとされます。 その中でも、この記事のテーマである仏教葬における代表的な忌み言葉は次の通りです。 ・浮かばれない ・浮かばれぬ ・迷う この他にも、お葬式の場では「繰り返すことが連想される」言葉は忌み言葉として、使用しないように注意が必要です。わざわざ、再三再四、たまたま、重ね重ね、いよいよ、度々、かえすがえす、重々、いろいろ、またまた、なおまた、等。